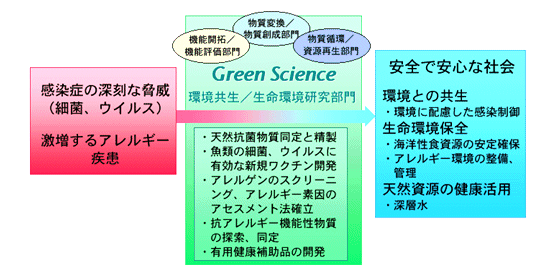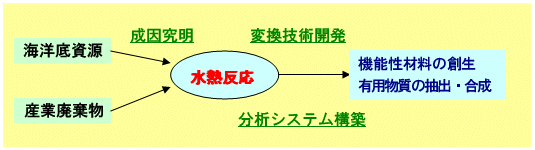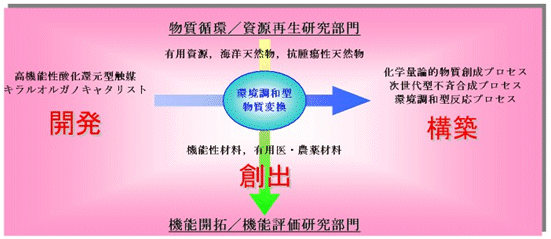本研究部門は,水熱反応をキーワードとし,海洋資源の生成機構の究明,機能性材料の合成,資源の
有効利用,廃棄物の再生利用のための技術開発,及びそれに関連する分析システムの構築を目指す。
水熱反応(高温高圧下の水が関与する反応)は,高温での固相反応や膨大なエネルギーを必要とする
真空状態での合成と比較し,水熱法は非常に温和な条件で材料合成が可能であり,環境調和型プロセス
として材料合成分野での応用範囲が広い。また,水熱反応は廃棄物の処理,処分,有効利用の分野へも
応用可能である。本部門では水熱反応を利用した機能性セラミックス合成や廃棄物有効利用に関する
研究を実施する。
地下深部でのさまざまな鉱物の生成に水熱反応が関与していることはかなり以前から知られていたが,
今日では海洋底の直接観察が可能となり,海底熱水鉱床を形成する活発な熱水活動中のチムニー群が
多数発見されている。海底には海底熱水鉱床だけでなくマンガン団塊やコバルトクラストなどの鉱物資源が
多量に存在しているが,これらの生成機構は未知の部分が多く,本研究部門ではこの生成プロセスを究明する。
水熱条件下ではさまざまな有機物が可溶化されることから,水熱反応を利用した資源の再利用や
有用資源の発掘が考えられる。例えばセルロースは水熱条件下で容易に分解され,糖類や有機酸などの
有用物質を生成する可能性がある。一般に水熱条件下での有機物の抽出や分解プロセスは非常に複雑で,
抽出物や分解産物の構造解析を含めてそのプロセスを解明するためには,効率的な分析システムを必要とする。
本部門ではこのような分析システムの開発も実施する。
![]()
![]()
本研究部門は,欲しいものだけを無駄なく環境にやさしく作る技術の開発を主眼とし,その応用としての
有用物質(生理活性天然物や機能性材料)創成を目的とする。そのために必要な技術として,各種触媒反応,
超高圧反応等の環境調和型技術に着目し,併せてそれに必要な方法論の確立を目指す。
有用物質をできるだけ環境に負荷をかけずに作り上げることは,現代合成科学分野での最重要事項の
一つとなっている。これに直接的に寄与するアプローチとして,化学量論的反応・触媒反応・無溶媒反応・
水溶媒反応等の開発が必要とされている。
このような時代の要求に真正面から取り組むため,本研究部門では,超高圧反応場を利用する
高効率的分子変換手法の確立,高選択的触媒反応システムの開発,高効率官能基変換手法の開発,
水溶媒中での酵素類似反応システムの開発,分子レベルからの触媒的プロセスの解明,光学活性物質の
効率的合成法の開発,それらの知見を駆使した物質創成プロセスへの展開を行う。併せて,これらの成果を
基盤として,有用医・農薬材料の合成,生理活性天然物の効率的合成,有用機能性材料の合成を行い,
機能性材料の開発を基本戦略とする「機能開拓・機能評価部門」との有機的連繋強化を図る。
![]()
![]()
本研究部門では、機能物質の探索と機能評価技術の開発を通じて、理学や生命科学、
医療への貢献を目標としています。参加研究者はそれぞれ、発光性色素、金属ナノ粒子、抗原ペプチド、
糖鎖、におい物質およびフェロモンと、物性の異なる研究対象について、機能を最大限に引き出し、
将来の応用にむけて研究をすすめます。その過程で必須となる機能評価技術の開発にも重点をおいています。
また当部門は、他の3部門で候補に上がってきた機能分子について積極的に機能評価、応用利用を試みる予定です。生物系の3グループは、外界と細胞の境界にある細胞膜上の情報受容分子について物質認識の
特異性と分子会合の研究と定量化を試みます。また、その認識の結果起こる細胞や個体の応答について
情報連関の分子機構を探ります。理学部のグループは、発光性色素の分子設計、金属ナノ粒子を使った
高感度ケモセンサーの開発をめざします。
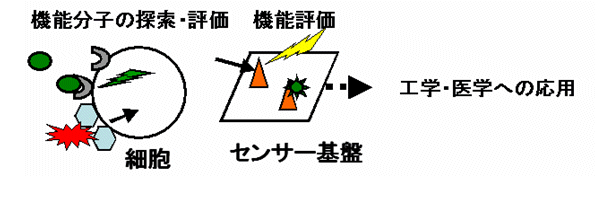
![]()
![]()
本研究研究部門は、「人類と環境との共生に関わる物質の挙動を解析し、それを生命維持に いかに生かすか」 を
研究テ?マに、主たる研究対象を環境因子としての「感染」と「アレルギー」に設定、その制御・克服に向けた
研究を推進する。具体的には、ヒト難治性病原細菌感染症に対する抗生物質非依存療法確立の一環として、
無尽蔵に存在する天然の抗菌リソースであるバクテリオファージを活用する治療法の開発と、従来にない
視点から腫瘍ウイルス増殖抑制分子の同定を目指した研究を行う。また、養魚類にとって深刻な脅威と
なっている細菌やウイルス感染症に有効な新規ワクチンの開発に結びつく研究として、これら病原微生物の増殖の
分子基盤解明に取り組む。以上は、抗生物質の使用量低減に寄与し、ひいては耐性菌の出現、医療費の増加、
生態環境破壊の抑止に働くであろうし、食資源の安定確保に役立つであろう。さらに、今や国民病とも言える気管支喘息、
アトピー性皮膚炎、花粉症などのアレルギー疾患の克服に向け、複雑なアレルゲンのスクリーニング法の開発、
アレルギー素因としての新指標の同定と検査法の開発研究を通じてアレルギー環境の整備改善と管理法を追及し、
加えて、アレルギー予防効果を持つ機能性物質の探索同定を目指す。また本研究部門では、膜分離技術を利用して
海洋深層水中の Ca 、 Mg の濃度比を変えることなく濃縮し、かつ阻害要因の Na を低減した深層水ミネラル調整技術を
開発し(県、民間と共同)、低コストでの深層水由来健康飲料の供給に向けた研究も実施する。