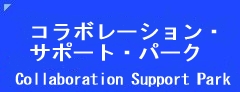公開日 2012年1月18日
さて本当に先日のオロゼイ訪問では考えさせられることが多かった。まちづくりという面で本当にイタリアはレベルが高いと思った。7000人の街から、多くの産業が生まれており、とんでもないビジネスの成功者が生まれている。そしてその人が地域の人から愛され、地域のことを本当に考えていた。
そして高知の中山間地域だって、少し考えればいくらでも変われるという確信を持てた。山から大理石が出なくても、きれいなビーチがなくても。ちなみに作業場からこっそりと家に大理石を持ち帰ってみた。もちろん割れて捨てられていたものですよ。今コースターに使っている。少しリッチな気分。
そういえば今、高知では多くの大学生が地域で活動している。もしかしたら僕もその一人なのかもしれない。
ときどき思い出し笑いするのだが、2年ほど前、上田先生に、「高知大学って学生を外にっていう雰囲気がありますよね。これって本来大学生が自分でやるべきで、ある意味甘い仕組みですよね。」
と言ったことがある。
「お前が言うか。」と笑われました。
あの時は偉そうなこと言ってすいません。本当に昔は怖いもの知らずだったので(笑)
最近、高知で感じる違和感。
街づくりや積極的に活動をなさっている方がまわりに多いことは高知県民である僕にとってはとても心強い。一緒に何かをやってみたいと思わせてくれる人が多い。
が、その人たちと活動しているであろう学生さんたちから違和感を覚える。
というのも、活動をしている学生さんとお話をすると、結構どこかで聞いたことがあるような、同じようなことばかりを言っていることがあるからだ。
いろんな活動をしている人に限って、その人の考えや思いが、難しい言葉に隠されている気がしてならない。地域の何に興味を持って活動しているのだろう?何を学びたいのだろうと・・・いう疑問が・・・。
僕は、大学生が地域活性化に寄与するなか、定義は分からないが「活性」に関われることってそんなに大きくないと思っている。にぎやかしはできるだろうが。大学に通いながら、バイトをしながらなどと言うとそこに割ける労力は決して大きくない思うのだ・・・たぶん地域づくりのプロが本気で仕事としてやってもなかなか地域って変わらないものだと思う。
もちろん休学をされて84プロジェクトに時間を割き、多くの成果をあげられている川村先輩は尊敬するというか、僕の言いたいところとは次元が違いますが。
僕は学生が大事にすべきは、その地域の活動からいかに自分がフィードバックをうけ、考えられる時間を持ち、大きくなるかだと思っている。地域で何か、コマのように働いて、人の意見を我がもののように取り込んでいる人にはそうとう恐怖感を覚える。
ちなみに大学1年のときはそういう感覚を僕も持っていた。地域で活動できる自分は特別というか、凄い、みたいな・・・。今になればはずかしい。みんなそういう道を歩むのなのかな?僕には幸いに協働する相手が、あまり積極的にあれしろ、これしろと言わなかった。ある意味何もしてくれない存在だったのが幸いした。
僕は大人が嫌いだ。
かしこいもん。
かしこい。
だから大人は使うものだと思い込んでいる。もちろん尊敬する人はたくさんいるし、ホントに嫌いなわけではないけど・・・。大学生はもっとそういう感情(?)を持つべきだと思う。信じすぎ。
本当に地域と大学生が協働するというのなら、責任を持って一緒に地獄か天国か知らんが、その果てまでランデブーすればいいと思う。でも4年という限られた期間という足かせが、大学生の自由さを奪っているように思う。それは地域側にとっても同じであるだろうけど。
大学生のよさって労働力としてじゃなくて、自由に考えられる時間と行動への責任が100%自分持ちにならないことだと思う。失敗が許されるというか・・・(←これは甘いけど)。
これから高知県の地域活性化に関わりたいと本気で思っている、もしくは動き始めて何か変わりたいと思っている学生にこそ、一から自分で全部を責任持ってやるか、もしくは本気でひとつの地域に入り込むことをしてほしいと願う。失敗しないであろう、大人の作った道を歩くことほど面白くないことはない。たくさん活動した人にはその経験から一般性や法則・理論、新たなハウツーを作り出してほしい。
僕は、学生は、学生として、学生が地域に入ることの本来の意味を考えるべきだと思う。絶対大人のコマにはならないと(笑)
いつまでも地域をうろうろして大学で色々してましたというのはもったいないと思う・・・。
話は変わるけど。
友人が昔言っていたが、『旅をする』ことは決して強い人のすることではないと。たぶん同感の人はいるかと思う。旅でできた道に責任は生じない。いいつながりはたくさんできても、悪いつながりは無責任に切ればいいのだから。だから旅で何かを見てきましたっていうのは見たり聞いたり感じたりつながりを作ったり、でもあくまでひとつの経験だと思う。地域活性化にも旅のような一面と、そこに住むようなしなやかさの両方が必要だろうと思う。
住むか、本にするか、研究するかなにかの材料にしなきゃ。就活の道具にというのはなんとなく僕は嫌いだ。そんな思いで地域に入ったら地域から使われるだけだと思う。
話は変わるけど、イタリアでは、本当に色々なところで大学生の僕を助けてくれる。イタリアという街、人が僕を育ててくれるように感じる。
昨日のアントネッロさんは仕事の空き時間でならスカイプが使えるから、君の調査のお手伝いをさせてくれと。それが私の喜びだからと、優しい笑顔で言ってくれた。友人たち、大学の先生たち、大学の友人や先輩たち、みんなが一緒に考えて助けあってお互いを高めあっている。こちらで勉強したいことを言えば資料を探してきてくれる友人。調査に連れて行ってくれる先輩。調査票の添削もしてくれた。
高知では決定的に学生同士の横のつながりが弱い。
同じ地域活性化という土俵におっていても学生同士のつながりがどれほどあるのだろう?
どんな学生団体に属して、何をしたかなんて関係ないと思う。何を考えて、どう成長したかかが本当に大事だと思う。大学で、たまに「色々活動していてすごいですね」とか後輩に言われるわけですが、それは心外というかつらいという感情に近い。何も僕のことを分かってくれていない。僕もたくさんの人のことを分からなきゃいけないんですが・・・。やっぱり僕はどうも人が苦手なもので・・・。
いっぱい活動したから、いろんなことを覚えたからすごいというのは、正直高校生まででいいと思います。
例をあげれば今大学で、僕の研究に興味を持ってくれている人がいないことが少しさみしい。しばらくこらパ~の前に研究成果を張り出させてもらったが、学生からは無反応。先生方はアドバイスをくれたのに・・・。なんで興味ないんだろう。ショボーン。
こちらではたくさんのアドバイスと環境を提供してもらえる。すべて仲間から。上っ面な難しい言葉ではなくて。辞書があれば僕の中一レベルの英語力でも議論は十分(言いすぎた7分くらい)にできる。そうなってほしい。
例えば僕自身、自分らで学生団体を作り、そこの代表をしばらくやっていたからだと思うんだけど、後輩に言いたいことは山ほどあるんです。でもやっぱり対等にお互いにアドバイスをしながら、いっしょにやることが大事だと思うから、待つこともしたい。僕が彼女らから学ぶことは本当にたくさんある。できれば僕からも学んでほしい。
最近のアドバイスは、「頑張れ」と「自分の負担になるくらいのことを何かやれ」、「ブログ書いて」くらいだと思う。いまだにブログを書いてくれないので、何とも影響力のない先輩なんだな~と落ち込む。
自称SMSはオープンな団体として、多くの授業の学生さんを受け入れたり、いくつかのゼミの学生さんたちとも日曜市で活動した。他の学生団体とのコラボもすれば、他大学との研究交流やそのほかモロモロやってきた。
一年生のときにお世話になった先生の影響もあるのだが、僕は基本的に放置するし、僕はこの留学でお世話になった先生にイタリアに放置してもらっている。実はいろいろサポートしてもらっていますが・・・。でもアドバイスがないと、登れない壁は登れないまま。だから僕は、先生たちから色々と機会と助言を与えてもらってきた。
僕のあこがれの先生のような、こなせなくはないけど、やれば負担になるようなアドバイス。これが、荒くてもいいけど大学生たちの中でできるようにならなくてはいけないと思う。それには横につながり、個人が考えて学んで動かないといけないと思う。
SMSでは、2月21日から2人がイタリアに留学してくるが、お金の一部を僕らがコツコツためてきた活動費からサポートしようと考えている。金額は小さくても、出店者さんから、日曜市のお客さんから頂いた、そして自分らが汗を流して稼いだ、本当に大切なお金である。今後も海外での学会発表や、日曜市の研究をするに関してかなりお金が必要である。今は全部先生任せになっているお金の面。基本的に僕は大人を使うんですが・・・
さすがに○つき先生(たち)にはお世話になりすぎだ。過労死させてしまう・・・。
ここも自立していかなきゃ、大人にならなきゃいけないと思う。ちょっとお金の取り方を勉強しようと思う。
僕は大人が嫌いだからお金のことも含めて、子供だけで学びの仕組みを作りたい。地域活性化の仕組みじゃなくて、そのあとの学生同士のお互いの高めあい。一度大学1年のときに先輩たちとこういう仕組みを作ろうとして挫折した。今はどっかに行ってしまった友人と二人で、こんな夢を話していたことを思い出した。そして僕は思いを受けて、そろそろ動きださないといけないなーとも思う。
今、日曜市でお世話になって子供なりに、自分なりにいろいろ学んで、そう思う。高知大学にはそんな大学になってほしい。というか、学生でそういう環境づくりをできると思うから。
こうやって学生と地域と仲間の間で、その機会と学習の仕組みがうまく作れていけたらいいなと思う。もちろん日曜市が元気になればいいと思うし、これからも一生続けるつもりです」。
こんなアホな僕をナマアタタカク見守ってくれる学部・また部門の先生たちには本当に感謝している。あと1年間で、僕なりにナマアタタカク見守ってもらったことへの感謝とお返し(仕返し)をするつもりです。
ふざけたことを真面目に書いて疲れたので、のろけようと思う。
「きっと違う環境は嫌でも強くなれるし、嫌でも成長できるで。だからといってそれに満足することなく、貪欲に生きてください。頑張っているとかこれでいいとかじゃなく、全部つかんで自分のものにしてください。」
彼女から手紙が届いた。その一部。熱いでしょ?自分で言うのもなんだけど、結構いい感じじゃないですか??まぁ文面だけ見るとここにはラブレターのラの要素も無いです。何とも痛いところであるが、完璧に僕の状況を見抜かれている。
こう何とも言えないところがね・・・。頑張ろうと思う。
こんな感じのアドバイスをしあえるSMSという団体を僕たちの力で作っていきたいし、将来的には、高知大学の学生が変わるきっかけにもなりたい。
だらだらまとまりも無く書いてしまいましたが、これが社会協働で学んだの僕の答えです。2月9日頑張りまーす。
NINO