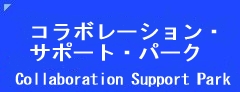公開日 2014年7月13日

7月13日(日)。えんむすび隊は高知市円行寺にあるDeerLandFarm岡崎牧場に伺いました。
岡崎牧場は鹿嶋利三郎さんが経営する牧場で、山地の急傾斜を活かして牛を放牧しています。牛乳を販売するだけでなく、牛乳を使ったソフトクリームやお菓子なども販売や動物と触れ合うオープンファームにも取り組んでいます。


学生たちは牛たちが草を食べる山地の放牧地に生えた木や枝の伐採作業をしました。
急斜面でのこぎりやハサミを使っての作業はなかなか大変なのですが、木々を切り倒すごとに視界が明るく開け、牛が草を食む姿を見るときついなりにも達成感があります。
この日は鹿嶋さんを筆頭に学生だけでなく、高知県庁の職員の方も一緒に17名で作業をしましたが、通常は2~3人で山地一帯の伐採をしているとのこと。作業後は鹿嶋さんたちの日頃の苦労に思いを馳せつつ、冷たくて美味しいソフトクリームを頂きました。
また、なぜこのような体験を大切にしているかを高知県の高知市域・地域支援企画員中越総括からお話を伺い、自分たちの体験の意味を考えました。

以下は、参加した学生の感想です。
◆農学部3年 女子
見晴らしのいい牧場での伐採作業は、少ししんどかったけれど気持ちのよいものでした。
すこし視界の広くなった牧場で草を食む牛を見ていると、達成感が沸いてくるのを感じました。
最近では「のびのびと生きている牛の牛乳が飲みたい」というお客さんが多いそうですが、納得です。私も今日改めてそう感じたからです。
また作業後に食べたソフトクリームのおいしかったこと!これだからえんむすび隊にたびたび足を運んでしまいます。(そろそろ自分で動き出さなくてはと考えているのですが…)
心に残ったのは、経営者さんや県の職員さんのお話です。
経営者さんは、自分でも草を刈りたいのは山々だが日々の作業が忙しく、とても追いつかないとおっしゃっていました。牛の世話には一日8時間ほどかかるのだそうです。
「牛乳だけ生産していたのでは採算が取れない」という、県の職員さんのお話も胸に残りました。
そこにしかない、魅力ある独自の商品を作り出すことが急務だということを改めて感じました。
今県や大学が一生懸命地域と連携しているのは、互いに支えあいながら新しい価値を見つけ出すためなんですね。
私も残りの学生生活で、新しい価値を見つけ出すためのお手伝いができればと考えています。
民法もぜひ学んでみたいです。
とても有意義な時間をすごすことができました。ありがとうございました。
◆人文学部1年 女子
自分の想像していた牧場と違っていた。自分の中では牧場は平面で傾斜があるなど全く想像していなかったから驚いた。今回、10数人で伐採したけど、人数が多くてもきつかったのに本来は2人ですると聞いて驚いた。人手不足を補うために今回のような体験型として一般の人にも体験してもらえば、早く作業が終わり、また、岡崎牧場の宣伝にもなるからいいと思った。
地域への提案として、せっかく急な斜面があるのだから、あの斜面を利用して、滑り台などを作れば子供が集まると思う。安全対策として滑り台の両サイドのヒモに電流を流し、牛から襲われる危険性を回避することが出来ると思う。
◆人文学部1年 女子
牧場整備ということで、木の伐採をしましたが、放牧場が山の斜面ということもあり、大学生10人、大人5人ほどでもかなりキツく、時間がかかりました。この作業を普段、農作業をされている方二人で、いつもの作業の間をぬって行うのはかなり難しいことだと思います。お手伝いできてよかったです。作業は暑さもあり、キツかったですが、楽しかったし、その分、ソフトクリームも美味しかったです。
岡崎牧場、前に一度観光、遊びで行ったことはありましたが、今回は牧場の方や、県の職員の方ともお話ができ勉強になりました。高知は特に山が多く、傾斜地で放牧というのは斬新で酪農家にとっても新しい道を切り開いてくれていると思う。
牧場のとなりでそこでとれたものを加工して売るというのも新しくてすごくいいと思いました。新しく何かを始めるというのはパワーのいることだから、すごいと思います。
私は高知県の活性化がしたいと思っているので、こういう風に様々な地域や現場へ直接足を運び、一緒に作業したりして、話を聞くことが出来るのはとてもうれしいし学ぶことができます。今回は県の産業振興を行っている方の話も聞くことが出来て良かったです。