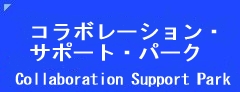公開日 2016年10月16日
土佐の伝統調味料として某テレビ番組でも紹介された葉ニンニクのぬた。この葉ニンニク、ニンニクの生長過程の葉を収穫したもので、ニンニクの芽とは異なります。原産は中国で、中華料理に重宝される柔らかい食感のマイルドな香味野菜なのですが、あまり日持ちがしません。
そんな葉ニンニクは、高知県をはじめ一部のニンニクの生産地など限られた地域でのみ、食文化が見られます。たとえば高知では、鍋に入れたり鯨と煮たり。中でもぬたは、ブリの刺身やカツオにもとても合う、高知県民のソウルフード(ソウルシーズニング?)。葉ニンニクと味噌と酢などを混ぜて作る、鮮やかな緑のペーストです。
一度食べたらいつの季節も食べたくなってしまうぬたですが、葉ニンニクに旬があるので、いつでも食べられるわけではありません。量販されているぬたの中には、葉ニンニクを使わず着色料で緑を入れたものも見られます。雰囲気は楽しめるものの、味はやはり別物です。本物のぬたを「いつでも食べたい!」と思い、移住後に葉ニンニクの栽培から加工まで手がける会社を立ち上げた、(株)アースエイドの嶋崎裕也さん。今回のえんむすび隊は、嶋崎社長の実践についてお話をうかがい、その土地の伝統文化を受け継ぎ、人も地域社会も活き活きと過ごすことに繋がる6次産業化について学びます。
お昼には、地元のコーディネータのご厚意で須崎産のお刺身やバケットを用意していただき、嶋崎社長がぬたを振舞ってくださいました。3種のぬたはどれも美味。「美味しい!」「刺身だけでも美味しいのに、さらに旨い」と、箸が進みます。
熱い思いと冷静な実情把握とを備えながら、直面する状況に向き合い、私利私欲に陥ることなく地域社会や自身の大切な人たちと共に「活きる」ことを大切に行動してきた社長の在り方から、学生たちは多くを学んだようです。
お世話になったみなさま、ありがとうございました。
以下に参加した学生の声を一部紹介します。ぜひご一読ください。
●人文学部国際コミュニケーション学科4年女子
本日は午前中に葉にんにくの植え付け、午後に実際の商品の試食とこの仕事を生み出した経緯をお聞きして事業の根本的な所を体験し、お聞きすることができました。
地域の郷土食であるぬたは、もしも家庭で作る文化が衰えていけば、そのものが消滅してしまう恐れもあったと思います。それを実際のレシピを商品化することで、伝統文化の継承にもつながっているのだと感じました。食本来の安全性、身体を健やかにしてくれる作用を最大限に生かした製品で素晴らしいものだと思います。こうした自然にも人間んにも有益な働き方に自分も参加していきたいです。
1から事業を起こしていく上で途方もない学習と試行錯誤があったと思います。それを着実にプロセスを積み上げている嶋崎さんのバイタリティは尊敬しました。
●地域協働学部地域協働学科2年女子
嶋崎さんのお話を聞いて一番印象に残ったのは出会いが大切、場数を踏んで経験値を上げることが大切だという事です。えんむすび隊への参加は初めてだったけど、自分の興味・関心の赴くままに自らアクションを起こして参加したというのはとても大切な財産になったと思います。
自分の経験値を上げる一つの手段としてえんむすび隊への参加はとても有意義でした。
●農林海洋科学部農芸化学科1年女子
どうして6次産業に取り組もうと思ったのか、オーガニック栽培にこだわる理由、人的ネットワークの大切さなどいろいろお話を聞くことができていい機会になった。私は目標やゴールが決まっていなくて迷っていますが、経験値を上げることが大切だと嶋崎さんからアドバイスをもらうことができて、何でも挑戦することの大切さに改めて気づいた。
高知にはまだまだ色んな食品があると思うので、光を当てて県外・海外に発信する活動に参加したいと思った。人的ネットワークを大切にしたい。