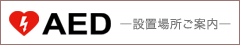公開日 2025年9月30日
高知大学の共通教育科目「土佐の海の環境学:柏島の海から考える」の一環として開催されるZoomによるオンライン座談会(ミニシンポ)を一般公開いたします。内容は下記の通りです。
記
第8回宿毛湾大学 オンライン座談会(ミニシンポ)
「南海トラフ大地震とコミュニティ防災」
日 時:2025年9月30日(火) 9:00-12:00(予定)
場 所:Zoomによるオンライン開催
対象者:大学院生、その他学生・教員や、学外の方も興味をお持ちの方ならば、どなたでも歓迎です。
参加方法:参加をご希望の方には、ZoomのIDを発行いたします。
メールでお送りしますので、下記URL(ないしQRコード)の入力フォームから、9/29(月)17時までに必要な情報をご入力下さい(土佐の海の環境学の受講者は不要です)。
URL:https://forms.office.com/r/YALLqgZ4JM

※この入力フォームに入力いただいた個人情報は、ご連絡や座談会への参加者把握等の目的以外には使用いたしません。
【内容】
問題提起:「南海トラフ大地震を見据えた柏島の課題と防災の備え」(神田優)
話題提供の講義1:「犠牲者ゼロをめざす 黒潮町の地震・津波対策」(村越淳)
話題提供の講義2:「里海の誇りと暮らしを残すために -「いつも」と「もしも」をどう繋げるか - 」(大槻知史)
パネル・ディスカッション(敬称略)
コーディネーター:石筒覚(高知大学地域協働学部准教授)
パネリスト(五十音順):
大槻知史(高知大学地域協働学部教授)
神田優(NPO法人黒潮実感センター理事長)
村越淳(黒潮町役場情報防災課課長)
【概要】
2024年8月8日、宮崎県の日向灘でM7.1の大きな地震が起こったことを契機に、気象庁は南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)を発出し、高知県内でも各所で緊張が走りました。特に沿岸部は、南海トラフ大地震が発生した場合、巨大な津波に襲われることが予測されており、どのように素早い避難を行い、その後の混乱を乗り切って、人的被害を最小化するかが問われています。
土佐の海の環境学の実習を行う柏島も、南海トラフ地震が発生すると、数分から20分程度で津波が到達すると予測されており、高台への素早い避難が必要になります。しかし、柏島の中には高齢者が多く、また狭隘な路地が倒壊した建物に塞がれることも起こると予測されているため、迅速な避難が可能か心配されています。また、柏島にはハイシーズンにはたくさんの観光客が訪れ、ダイビングや海水浴を楽しんでいるため、観光客の避難をどう誘導するかという点も大きな課題になっています。
本ミニシンポでは、同様に津波避難が課題となっている高知県黒潮町役場で防災を担当する村越淳氏をお招きし、同町の防災への取り組みについてお話をしていただきます。黒潮町では、町を14の地域に分け、それぞれの地域で町職員190名が分担して「防災地域担当」を務め、住民と共に減災の対策などを考える仕組みを導入しています。黒潮町では最大34mの津波の到達が予測されているため、ハード面の対策として、避難場所やそこへ通じる避難道(260本)を整備すると共に、到達時間までに避難できない地区には垂直避難のための津波避難タワー(6基)を建設しています。ソフト面の対策としては、浸水想定区域の約3800世帯を対象に、「戸別津波避難カルテ」を作成、住民とリスクを共有して発災に備えるほか、住民による自主防災組織が地域の防災力向上を担っています。
柏島でも発災時の、高齢者避難の支援や、四国本土につながる橋が落ちた場合の炊き出しや水確保などの面で、地域コミュニティの自主的な活動が課題になってきています。
本座談会では、対策が全国で注目される黒潮町の事例を起点に、南海トラフ地震が起こった際の対応における地域コミュニティの役割と課題を議論します。