ご挨拶

我が国は、戦後「自動車」と「半導体」で世界に類を見ない復興を成し遂げてきましたが、これを実現の過程で高効率化が常に求められ、その結果「なぜ?」と考える暇はなく、視野は自ずと狭くなり、思考は画一化して如何に上手くやるかに終始して来たように感じます。
その結果がどうかはさておき、何となく閉塞感を感じる世界が自分の身の周りを覆っていることを日々感じながら「この閉塞感の正体はいったい何なのか?」それを明らかにしたい!「こんな世界を希望ある世界に変えて行きたい!」という思いから、ご縁のある色々な世代や色々なご経験の異なる方々と共に、構想から約10年、「思索」と「対話」を繰返しながら、皆で立上げ運営してきたのが高知大学の希望創発センターです。
この希望創発センターでは、社会人の方々を大学にお招きし、学生と共に約1年間、属性を消して生活者というフラットな関係性を築きながら「なぜ?」と考えることをど真ん中に据えて活動を続けてきました。その結果、参画者の多くの方々が変容して行く姿をいくつも目の当たりにしてきました。
このSIP事業での我々の取組みは、希望創発センターでの経験をもっと多くの市民の方々にも開放し、経済原理で繋がりがちな人と人の繋がりを「人」として繋がっていくことを中心におきながら、みなさんと共に希望ある社会を愉快にゆったりと創って行くことで、結果としてイノベーションの創出が起り、経済も持続的に循環し、自治する地域が立ち上がり、各地域の顔である多様な文化が育まれ、一人一人が幸せな生き方のできる社会を本気で実現しようとチャレンジするものです。どうかよろしくお願い申し上げます。
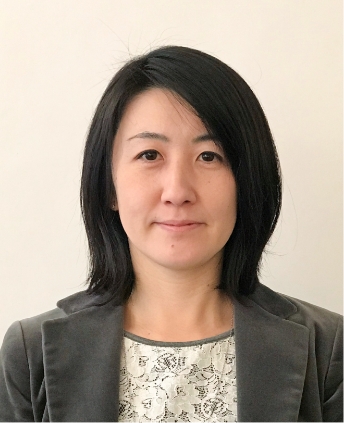
大学教員として日常的に大学生の皆さんと接するようになって久しいですが、中には、受験競争を乗り切って大学に入学したものの、大学受験の先にあるべき、学ぶ目的や学びへのモチベーションが持てないでいる学生がいます。そのような彼らは、将来への不安を募らせつつも、やりたいことが見つからず、しかし特に積極的に挑戦したり行動を起こすこともなく、忍んで過ごしていることも多いように感じます。
大学で学ぶ目的やモチベーションを見いだせない1つの要因は、彼らの学習観が非常に限定的で、予め正解を用意された試験に向けた勉強が学習であるという環境に過剰適応してしまっているところにあります。本当は世界はもっと広く、学びはもっと愉しいはずなのに、それを知る機会が大学教育の中で持てていないということではないでしょうか。もちろん、授業という効率的な学習機会を通して、世界中に存在する多様な知識を獲得することはできます。しかし、本当に学びを愉しいと感じ、高いモチベーションを持つためには、教科書や教授による講義から正解を与えられる学習の方法ではなく、自ら問いを立て、探究する活動こそが効果的なはずです。すでにそのような探究活動を導入した授業も多く実施されているのでは、と思われるかもしれませんが、授業内での活動は教員が枠づけ、結果を成績という形で評価されるという点で、真に学生主体の活動ではありません。
SIP事業では、「教える―教わる」相互行為を一方向の固定的な関係ではなく双方向の流動的な関係とすべく、大学内外に存在する多様な学習者をネットワーク化し、協同的な学習の環境と文化、つまり「学び合い」が創発する生涯学習プラットフォームを構築しようとしています。このプラットフォームに参画する学習者それぞれが自己効力感を高め、社会関係資本を醸成し、多様なロールモデルを獲得し、共に活動する仲間を見つけ、自己変容と社会変革を促進していくことを目指しています。もしこのプラットフォームに少しでも興味を持っていただけましたら、私たちはいつでも門戸を開いておりますので、ぜひ一緒に協働しましょう!

インターネットやSNS、ビッグデータ、AI、その他メディアテクノロジーの発展・普及は、人々が日々触れるコンテンツや広告を個別最適化し、それぞれの興味・関心に基づいた知識や情報の獲得を容易にしました。また、近い趣味や価値観を有した人と空間を隔ててつながり、日常的にコミュニケーションを楽しむことも可能になりました。もちろん、フィジカルなコミュニティから解放されたことや、世界中の人や情報にアクセスするためのコストが大幅に低下したことは、それまでとは比較にならないほど大きく開かれた出会いや学びの機会が実現したという意味で、「良いこと」だと言えます。
しかし,同じ趣味や価値観を有する人のみと関係性を結び、好きなもの・心地よいものに囲まれて生きられるということは、その反面、価値観の異なる人や、良く分からないものには触れずに生きられるということでもあります。フランスの哲学者ベルナール・スティグレールは、冒頭に述べたテクノロジーが導きつつあるのは、個々の個性(特異性・唯一性)や多様性が拡大した社会ではなく、欲望や消費がコントロールされ、類型化・蛸壺化の進んだ閉鎖的な世界であることを予見しました。
このSIPの取り組みは、もしかしたら機会が減少しつつあるかもしれない、「自分とは異なる他者の視点に出会う」ということを核としたプロジェクトだと思っています。多様な人々の表現に触れる。そこから触発され、自分も何かを表現してみる。その積み重ねの中で、異なるバックグラウンドを持った人と交流したり、未知の物事にアプローチしたりすることの面白さを実感していく。それは、日々の生活を豊かにするものであると同時に、新しい発想やイノベーションのための基盤にもなると思います。このSIPの取り組みを通じて、そのような触発・創発するコミュニケーションを促すようなプラットフォームを構築していけたらと考えています。

