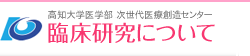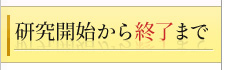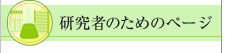「臨床研究に関する倫理指針」改正内容 (2008年7月31日改正 2009年4月1日施行)
① 倫理審査委員会
- 設置者に、特定非営利法人、国立大学法人等を追加したこと。
- 外部の倫理審査委員会に審議を依頼することができるようになったこと。
- 軽微な事項の審査については迅速審査が許容されたこと。
- 設置者は、倫理審査委員会の手順書を作成すること。手順書・名簿・会議の記録の概要を公表すること。
- 設置者は、委員会名簿、開催状況等を毎年1回厚生労働大臣等に報告する。
|
② 健康被害に対する補償
医薬品または医療機器を用いた介入研究を実施する場合には、被験者に生じた健康被害に対する補償のための保険その他必要な措置を講じる。 |
③ 教育
- 研究者は研究前に講習等の教育を受けること。
- 臨床研究機関の長は、研究者が必要な教育を受けることを確保すること。
- 倫理審査委員会の設置者は、委員の教育及び研修に努める。
|
④ 臨床研究計画の事前登録
研究責任者は、侵襲性を伴う介入研究の場合は、予め公開データベースに研究計画を登録する。 |
⑤ 臨床研究の適切な実施体制の確保
- 重篤な有害事象等に対して、手順書を作成する。
- 重篤な有害事象等が発生した場合、研究責任者及び臨床研究機関の長がとるべき対応を明確にする。
- 侵襲性のある介入研究での予期せぬ有害事象への対応、公表、厚生労働大臣への報告。
- 指針への重大な不具合があった場合への対応、公表、厚生労働大臣への報告。
- 研究責任者は、研究の進捗状況、中止、終了を報告すること。
- 必要に応じて研究が指針に適合しているか自己点検・評価をすること。
- 厚生労働大臣等が実施する実地又は書面による調査に協力すること。
|
⑥ 観察研究における試料等
- 介入研究と観察研究の定義を明確にして区別をしたこと。
- 人体から採取した試料等を用いる場合と用いない場合の観察研究のインフォームド・コンセントの手続きを明確化したこと。
- 既存資料等、匿名化、連結可能匿名化等を定義したこと。
- 試料等の保存、研究開始前に試料等の利用、他機関の試料等の利用につき疫学研究指針に習って規定したこと。
|
〈ページの最初に戻る〉