国際共同研究、医工連携、国内初の臨床研究実績の踏襲
光線医療センターの各国大学との連携体制及び東京工業大学生命理工学院や大阪大学工学研究科などとの医工連携体制、また脳性麻痺再生医療研究センターが国内初の臍帯血投与の臨床研究を実施した実績を、臨床研究伴走プログラムの中で若手研究者が踏襲することにより、高知大学が本領域における研究をけん引します。
本プログラムでは、(1)先端医療フェロー(自身の研究及び研究支援)、(2)次世代医療創造センターの研究支援・外部人材の活用、(3)RYOMA3の活用が一体となったタスクフォースを組むことで効率的で強固な研究体制と支援体制を図ります。
医学部長を事業責任者とし、本事業達成をミッションとするチームを設置。
課題や達成目標に応じてサブチーム(臨床研究伴走プログラム構築・研究力向上研修プログラム作成・外部との共同研究推進検討
等)を設置し、臨床研究伴走体制構築に関しては、サービス機関(CRO)への委託により組織立ち上げや臨床研究伴走に特化した専門人材をアサインします。
臨床実習生等の指導と臨床研究に重点を置く臨床指導医(先端医療フェロー)を配置し、「臨床指導医─専攻医─研修医─臨床実習生」の屋根瓦式指導体制の構築により、医師の働き方改革とともに研究・教育体制を強化します。
教えられた人が、次に教える側に回る。
先端研究フェローが増えるごとに医師の働き方改革とともに教育・研究体制の強化が進む。


本事業では先端医療学推進センター(先端医工学部門:光線医療技術等、再生医療部門:臍帯血の臨床研究、再生医療等製品の開発推進等、情報医療部門:心筋症ゲノムコホート等)を対象とし、事業終了後において他診療科に展開します。
医療従事者、生物統計家などの研究支援人材(PMDA出向経験者含む)が所属する次世代医療創造センターの人材増員、及び外部人材を活用する。
1997年に新薬の承認に向けた臨床試験を管理する組織として高知大学医学部附属病院に開設された「治験管理室」が元となり、 2013年に国際基準の医学研究に対応した、より安全かつ有益な医療技術の開発支援に取り組む「次世代医療創造センター」として新たなスタートを切りました。国内外のネットワークの発展により、臨床試験・治験が急速に大規模化・多様化する中で臨床研究・治験に協力してくださる方々の人権を守り、安全・適正・円滑に研究が実施できるようにさまざまな支援を行い、社会に貢献しています。
【高知大学医学部附属病院】次世代医療創造センター全国と比較しても“課題先進県”である高知の課題解決に向けて新たなテクノロジーを医療へ柔軟に取り入れるため、目標を共有する産学官の関係者が部局や所属機関の垣根を越えて、パートナーとして研究開発成果の検証・社会実装、イノベーションマインドの醸成などを実践することができる「地域共創の場」として高知市内中心部に開設された拠点です。


医学情報センターが長年運用・蓄積してきた40年間38万人分の仮名化データベースRYOMA2(Retrieval sYstem for Open Medical Analysis2)を、効率的に電子化医療情報から臨床的知見や予測を導き出せるインターフェースのシステム(RYOMA3)へと発展させ、活用します。

データベースを活用することにより、全国初のメディカルデータマイニングコースと環境保健学コース統合による公衆衛生大学院を四国初設置。また、病院経営プログラムやヘルスケアイノベーションコースなど学び直しの機会の創出と多様化につながります。
先端医療フェローが公衆衛生大学院で系統的に学ぶことで、自らの研究を強化できます。
光線医療センターの各国大学との連携体制及び東京工業大学生命理工学院や大阪大学工学研究科などとの医工連携体制、また脳性麻痺再生医療研究センターが国内初の臍帯血投与の臨床研究を実施した実績を、臨床研究伴走プログラムの中で若手研究者が踏襲することにより、高知大学が本領域における研究をけん引します。

RYOMA3を活用し、限られた研究時間内に効率的にフィージビリティ調査を実施することでより早く研究に着手し共同研究者をけん引することができます。また、社会人大学院生に単位を取得しやすい環境を提供することが出来るため、大学院生の増加に寄与することも期待されます。
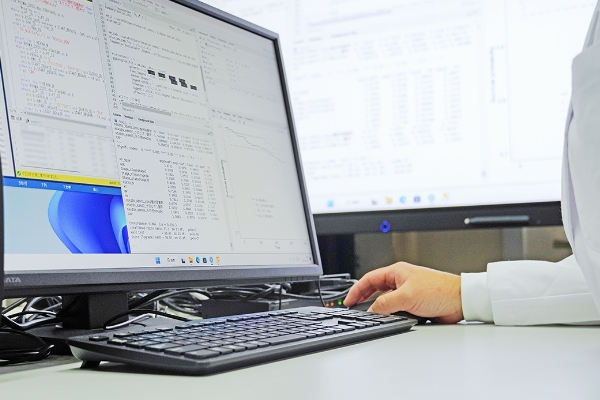
既存の大学院教育課程において、医療情報から病態の予測モデル等を開発する教育を実施しています。RYOMA3のクラウド環境で統計解析ソフトウェアを用いてAIを用いた診断補助ツールの開発や、SaMDのリアルワールドデータを用いた定期的評価を実行することができます。
