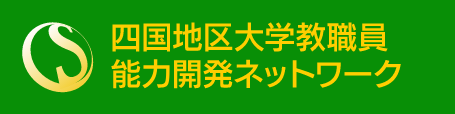- 2月5日令和7年度「授業について考えるランチセミナー」<学生が自ら考え主体的に学習するための授業づくり>が開催されました。
- 1月20日令和7年度「授業について考えるランチセミナー」<授業へのAIの活用>が開催されました。
- 12月4日令和7年度「授業について考えるランチセミナー」<学生の能動的な学びを促すチーム基盤型学習 TBL>が開催されました。
- 10月30日令和7年度「授業について考えるランチセミナー」<学生の学習への動機づけを高める授業づくり>が開催されました。
- 10月9日令和7年度「授業について考えるランチセミナー」<通信制大学の学びから対面授業の意義を考える>が開催されました。
- 8月1日令和7年度「授業について考えるランチセミナー」<学習評価の原則と方法>が開催されました。
- 7月4日令和7年度「授業について考えるランチセミナー」<授業時間外学習を促す授業設計>が開催されました。
- 5月29日令和7年度「授業について考えるランチセミナー」<自己調整学習の視点からオンデマンド型授業を考える>が開催されました。
- 5月8日令和7年度「授業について考えるランチセミナー」<合理的配慮が必要な学生への支援>が開催されました。
- 3月10日令和6年度「授業について考えるランチセミナー」<障害学生に対するキャリア支援>が開催されました。
FD・SDの取り組み
HOME > FD・SDの取り組み
FD・SDの取り組み
FD・SDの取組について
学びの質保証ユニットでは、教職協働の視点から、教職員の能力開発のためのさまざまな研修を実施しています。研修は主にワークショップ形式で実施され、参加者の主体的な学びを重視しています。
イベント events
新任教員研修プログラム

高知大学新任教員教育研修プログラムでは、本学の大学教員として新たに採用された者を対象に、業務を遂行するに当たって必要となる教育・学生支援の基本的な事項に関する研修並びに授業の内容及び方法の改善など教育力向上に関する研修を提供しています。
対象者・修了要件
対象者
新たに採用され、国立大学法人高知大学職員就業規則、国立大学法人高知大学有期雇用職員就業規則又は国立大学法人高知大学特任職員就業規則の適用を受けることとなった教授、准教授、講師及び助教(特任職員を含む)。
修了要件
対象者は、その採用の日から3年を経過する日の属する年度末までの間に、全学教育機構会議が別に定めるところにより、12研修以上を受講することが求められます。
ただし、医学部附属病院で診療に従事する者その他の特別の事情があると認められる者については、全学教育機構会議の議を経て、受講を免除することができます。
前項の規定に基づき必要な研修を受講し、新任教員教育研修プログラムを修了した者には修了証を授与します。
ただし、医学部附属病院で診療に従事する者その他の特別の事情があると認められる者については、全学教育機構会議の議を経て、受講を免除することができます。
前項の規定に基づき必要な研修を受講し、新任教員教育研修プログラムを修了した者には修了証を授与します。
- 新任教員研修プログラム受講要領(PDF)
本年度の開催予定
-
2025年4月7日大学授業入門
-
2025年4月7日公開開始グループワークのはじめ方/失敗しないための導入とチームビルディング(オンデマンド受講)
-
2025年5月14日申込締切授業改善支援プログラム(MSF, Midterm Student Feedback, 授業中間期での学生からのフィードバックに基づいた授業改善支援)
-
2025年9月2日講義に小グループ・ペア学習を取り入れた授業デザイン
~考え方と進め方~ -
2025年9月3日・4日学生の学びを支援する授業準備ワークショップ
-
2025年10月2日グループワークのはじめ方/失敗しないための導入とチームビルディング(対面開催)
-
2025年10月24日申込締切授業改善支援プログラム(MSF, Midterm Student Feedback, 授業中間期での学生からのフィードバックに基づいた授業改善支援)
-
2025年12月1日公開開始シラバスブラッシュアップセミナー(非同期型研修)
-
2026年2月2日新任教員のためのリフレクションセミナー
-
2026年2月2日グループワークのためのファシリテーション入門
-
2026年2月3日学生の主体的な学習を促す非同期型オンライン授業
-
2025年4月~授業について考えるランチセミナー
SPOD関連研修

SPOD(四国地区大学教職員能力開発ネットワーク)は、教職員の能力開発(FD・SD)を目的として組織された、四国地区の高等教育機関によるネットワークです。
SPODでは、FD・SDに関して、研修プログラムの標準化や共同開催、講師派遣プログラムなどの取組を行っています。
FDでは、コア校である愛媛大学、香川大学、高知大学、徳島大学が実施する新任教員研修のプログラムを標準化し、4校のいずれで受講しても、受講完了者には受講証明書が発行されます。
SDでは、「大学人・社会人としての基礎力養成プログラム」、「次世代リーダー養成ゼミナール」などについて、全加盟校から参加者を募り実施しています。
また、毎年8月には3日間にわたってSPODフォーラムを開催し、加盟校はもちろん加盟校外からも多数の参加者が集まって、高等教育についてのさまざまな課題を共有し合う場となっています。
高知大学が開催する研修のうちからも、SPOD加盟校の教職員が受講可能となるように開放しているものがあります。
SPODでは、FD・SDに関して、研修プログラムの標準化や共同開催、講師派遣プログラムなどの取組を行っています。
FDでは、コア校である愛媛大学、香川大学、高知大学、徳島大学が実施する新任教員研修のプログラムを標準化し、4校のいずれで受講しても、受講完了者には受講証明書が発行されます。
SDでは、「大学人・社会人としての基礎力養成プログラム」、「次世代リーダー養成ゼミナール」などについて、全加盟校から参加者を募り実施しています。
また、毎年8月には3日間にわたってSPODフォーラムを開催し、加盟校はもちろん加盟校外からも多数の参加者が集まって、高等教育についてのさまざまな課題を共有し合う場となっています。
高知大学が開催する研修のうちからも、SPOD加盟校の教職員が受講可能となるように開放しているものがあります。
全学FDフォーラム

全学FDフォーラムは、さまざまな高等教育に関するトピックの内から、高知大学が直面する教育上の課題をテーマに毎年1回開催されています。
全学FDフォーラムという名称ですが、近年は教員と職員の知恵を結集して課題解決に向かうことが求められており、また、テーマによっては学生の参加を求めて開催されることもあります。
全学FDフォーラムという名称ですが、近年は教員と職員の知恵を結集して課題解決に向かうことが求められており、また、テーマによっては学生の参加を求めて開催されることもあります。
これまでの実績
- 全学FDフォーラム2023「学習環境の安全安心を考える-主体的な学びを支えるもの-」
- 全学FDフォーラム2022「学生を主体的な学びに導くオンライン授業-Moodleを活用した授業デザインと授業外学習の工夫-」
- 全学FDフォーラム2021「学生の主体的学びを導くオンライン授業-オンデマンド授業とハイフレックス型反転授業-」
- 全学FDフォーラム2020「卒業後を見据えた教育の質保証へーAP事業4年間の報告―」
- 全学FDフォーラム2019「ティーチング・ポートフォリオについて」
- 全学FDフォーラム2018「教育の内部質保証の構築にむけて-内部質保証ガイドラインと教学IR-」
- 全学FDフォーラム2017「質保証の基盤構築に向けた「地域協働による教育」の多面的評価指標の実践的検証」
FD・SDウィーク

FD・SDウィークは、毎年、第1学期か第2学期のいずれかに、3週間から4週間にわたって、高知大学の授業を教職員に公開するイベントです。
この取組では、従来の授業公開を見直し、教員は、授業を参観することで、自らの授業改善のための気づきを得ることを目標としています。また、職員は、授業を参観することで、高知大学の教育に対する理解を深め、自らの大学職員としての業務を振り返る機会とすることを目指しています。
実施にあたって、参観者はWeb上で参観登録から授業担当者へのフィードバックまでを記録します。
この取組では、従来の授業公開を見直し、教員は、授業を参観することで、自らの授業改善のための気づきを得ることを目標としています。また、職員は、授業を参観することで、高知大学の教育に対する理解を深め、自らの大学職員としての業務を振り返る機会とすることを目指しています。
実施にあたって、参観者はWeb上で参観登録から授業担当者へのフィードバックまでを記録します。
授業参観者の声
教員
授業進行や内容がわかり、これから実際に授業を担当するうえでためになった。取り入れられる点が色々とあったので、参考にして実践したい。
事務職員
日常の業務のみでは学生が普段どういった講義を受けているのか、また、教員がどういった授業を行っているのかについて知ることができないため、授業を参観することで本学の教育について考えるよい機会をいただけたと思います。
授業について考えるランチセミナー
(徳島大学・高知大学・香川大学共催 SPOD開放プログラム)
お昼休みに食事をとりながら気軽にご参加いただけるFDプログラムとして、徳島大学・香川大学と共催でオンラインのランチセミナーを開催します。ランチセミナーは、8月と3月を除く毎月第2、第3木曜日の 12:05~12:50 に開催します。
令和7年度のスケジュール
| 日程 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 4月10日(木) 4月17日(木) |
合理的配慮が必要な学生への支援 | 合理的配慮が必要な学生に対して、授業において教員は何ができるでしょうか。授業作りの工夫や学生への対応について考えていきます。 |
| 5月 8日(木) 5月15日(木) |
自己調整学習の視点からオンデマンド型授業を考える | オンデマンド型授業において、動画視聴のみで終わっていませんか?学生の主体的な学びを促進するため、自己調整学習の視点からの実践例を紹介します。 |
| 6月12日(木) 6月19日(木) |
授業時間外学習を促す授業設計 | 課題の出し方や学生の動機づけなど授業設計の工夫を通じて学生に授業時間外学習を促す仕組みについて考えます。 |
| 7月10日(木) 7月17日(木) |
学習評価の原則と方法 | 授業で行う評価には成績をつける以外にも様々な役割があります。今回は評価の原則や留意点のほか、どのような評価方法があるかを中心に見ていきます。 |
| 9月11日(木) 9月18日(木) |
通信制大学の学びから対面授業の意義を考える | コロナ禍以降、対面授業の意義が問い直されています。そこで、通信制大学の学びを見て、そこから逆説的に対面での授業の意義を皆さんと考えます。 |
| 10月 9日(木) 10月16日(木) |
学生の学習への動機づけを高める授業づくり | 学生の学習への動機づけを高めるための理論をもとに、授業設計の工夫や授業中に実践できる取り組みについて具体的な方法を紹介します。 |
| 11月13日(木) 11月20日(木) |
学生の能動的な学びを促すチーム基盤型学習 TBL | TBLは反転授業の一種で、知識の獲得を目的とした授業に適した、学生の能動的な学習を促す授業方法です。その手法と授業での実践例を紹介します。 |
| 12月11日(木) 12月18日(木) |
授業へのAIの活用 | 最新のAI技術を活用した効果的な授業方法や実践事例を紹介します。教育現場での新たな可能性を一緒に探りましょう。 |
| 1月 8日(木) 1月15日(木) |
学生が自ら考え主体的に学習するための授業づくり | 学生が自律的に学習に取り組むことができる仕組みとして、課題発見学習を取り入れた具体的な実践事例をもとに授業づくりのポイントを紹介します。 |
| 2月12日(木) 2月19日(木) |
社会人大学院生の学びと支援 | 生涯学び続ける社会を背景として社会人大学院生が増加しています。社会人大学院生の学びと支援の在り方について紹介します。 |
※各テーマ2回実施します。内容は開催日ごとに異なります。
時間 12:05~12:50(ランチセミナー形式で実施します)
場所 オンライン(Zoom) 開催
TA・SA講習
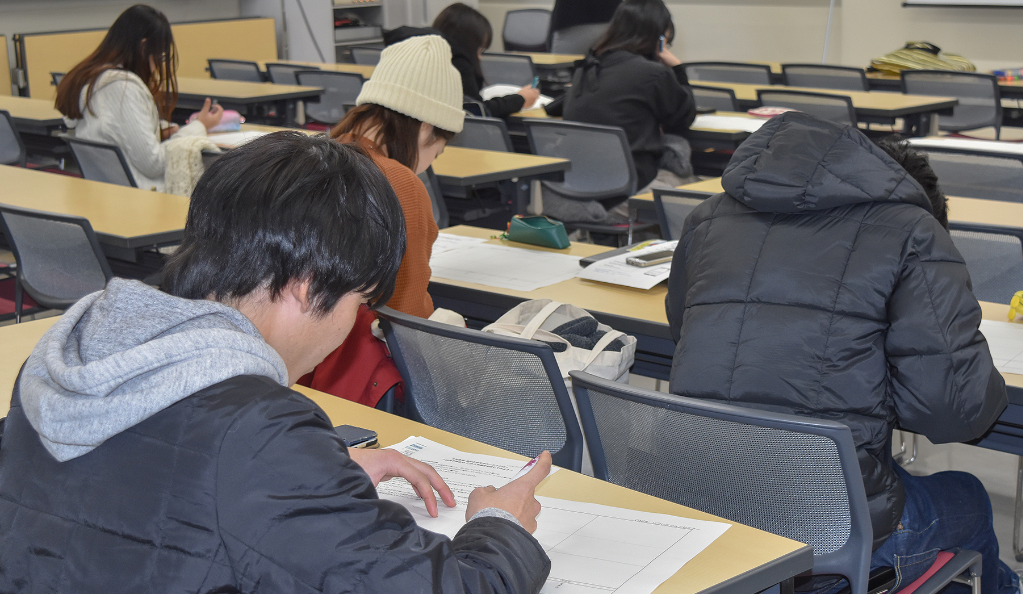
TA・SA講習は、ティーチング・アシスタント(以下「TA」という)として採用されることを希望する大学院生、並びに、スチューデント・アシスタント(以下「SA」という)及び学生ファシリテーターとして採用されることを希望する学生に対し、本学の教育の一端を担うことの意義や、受講生・教員を支援するために必要な知識とスキルを理解することを目標としています。TA講習は、将来大学教員になることが期待される大学院生に対するプレFDとしても位置付けられています。
研修内容
- オリエンテーション
- TA・SAの業務内容
- 職員としての心得
- 受講生への接し方とハラスメント防止について
- 事務手続きに関すること
- 講習のふりかえり
本年度の開催予定
TA・SA講習はオンラインによる非同期型研修として実施します。実施時期は下記のとおりです。
- 春季TA・SA講習:3月~8月(標準受講期間:3月下旬まで それ以降は予備受講期間)
- 秋季TA・SA講習:9月~2月(標準受講期間:9月下旬まで それ以降は予備受講期間)
※高知大学moodle 上に教材を掲載しますので各自で研修に取り組みます。
moodleコース上の全ての課題を完了した方へは修了証が発行されます。
moodleコース上の全ての課題を完了した方へは修了証が発行されます。
TA・SA講習の基本的な考え方
TA・SAは本学の非常勤職員に位置づけられます。したがって、TA・SAは学生の身分のまま受講生を支援する業務に携わることになります。受講生から見れば、場合によっては教員と同じ立ち位置に見えることもあります。
こうした場合、先輩として上から目線で受講生を指導するのではなく、受講生が質の高い学修成果をあげるために、TA・SAとしてどのような支援が必要であるかを考え、担当教員と相談しながら支援を実施していくことが重要になります。
このためには、支援する授業科目の専門知識だけでなく、受講生や教員とのコミュニケーションをとるための力や、クラスをマネジメントする力などが求められます。ハラスメントやメンタルヘルスに関する知識もある程度必要となります。
TA・SA講習は、こうした考え方に基づいて実施されます。
こうした場合、先輩として上から目線で受講生を指導するのではなく、受講生が質の高い学修成果をあげるために、TA・SAとしてどのような支援が必要であるかを考え、担当教員と相談しながら支援を実施していくことが重要になります。
このためには、支援する授業科目の専門知識だけでなく、受講生や教員とのコミュニケーションをとるための力や、クラスをマネジメントする力などが求められます。ハラスメントやメンタルヘルスに関する知識もある程度必要となります。
TA・SA講習は、こうした考え方に基づいて実施されます。
その他の研修
学びの質保証ユニットでは、下記の研修を定期的に開催しています。
ファシリテーション力養成道場

学生を対象として、ファシリテーション力養成道場を開催しています。2日間の道場では、ファシリテーションについての基本的な考え方を学ぶとともに、いくつかのグループワークの中で実際にファシリテーションを実践することができます。
道場の主なスケジュール
1日目
オープニング:趣旨の理解/アイスブレイク
FT(ファシリテーション)の考え方と基本を身につける(1)
FTの考え方と基本を身につける(2)
グループプロセスを観察する
FT(ファシリテーション)の考え方と基本を身につける(1)
FTの考え方と基本を身につける(2)
グループプロセスを観察する
2日目
アイスブレイク~模造紙にイロイロ書いてみよう
FG(ファシリテーション・グラフィック)の基本を身につける
FGのための図解の方法と板面の使い方
総合演習
FG(ファシリテーション・グラフィック)の基本を身につける
FGのための図解の方法と板面の使い方
総合演習
参加者の声
難しい内容かと思って構えていましたが,2日とも楽しく仲良く過ごせました。
学んだことをすぐに体験しながら行うスタイルが良かったです。
何よりも楽しい要素が多かった。かつ,悩めた。
いままでの話し合いの方法と全く違う方法で,うまく話し合いができるということを知った。
基礎的なことを学べたことは非常に満足ですが,これからの努力がもっと必要だと感じました。
学んだことをすぐに体験しながら行うスタイルが良かったです。
何よりも楽しい要素が多かった。かつ,悩めた。
いままでの話し合いの方法と全く違う方法で,うまく話し合いができるということを知った。
基礎的なことを学べたことは非常に満足ですが,これからの努力がもっと必要だと感じました。
パフォーマンス評価・リフレクション面談等に関するFD研修

本学で身に付けてほしい「10+1の能力」の評価目的・方法の確認や面談の効果向上を目的として、教育ファシリテーターやアドバイザー教員等を対象としたパフォーマンス評価とリフレクション面談に関するFDを実施しています。