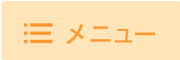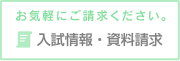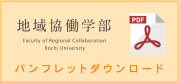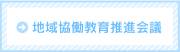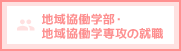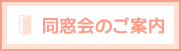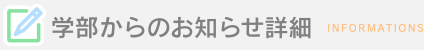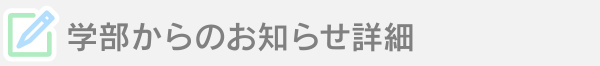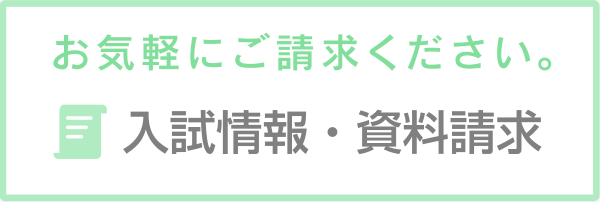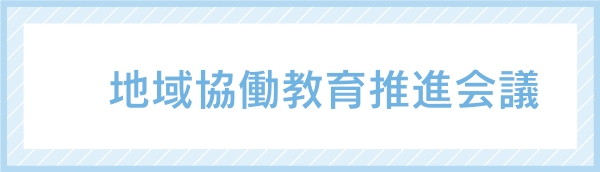11月15日、黒潮C記憶の記録と継承チームは、室戸市を訪れました。
10月11日に職員組合・青年部のご厚意で実現した情報交流会の第二弾として、遠洋漁業の町・室戸の当時に触れられる景観の断片やそれらに纏わる記憶を、よそ者である学生が学ぶ。教わったことを学生が解説しながら、現在の室戸について青年部の方々から教わる。そんなまちあるきをしたい。先週いただいたご助言を受け、室津港周辺を再訪しました。
今回は、室戸ご出身でご家族が船員だった方と一緒に、元船員さんらが出航・入航時に通っておられた元料亭の一つにお邪魔し、じっくりお話を伺いました。
地域の産業を担う繁華街だった室津港周辺には、いくつもの料亭がありました。当時の船員さんは稼ぎがよく、仲居さんからすると「チップだけで生活できる?!」と思えるほどの羽振りだったようです。
「今は閉めました」と仰るそのお店を女将と料理長として営んでおられたご夫妻に漁船員さんの往時の様子を伺うと、「入港したら盆であり正月」というくらいよく呑まれた、と言います。宴会時は懐石料理や皿鉢料理がほとんどで、マンボウが人気だったり、冬には猪鍋を出したりもしたそうです。見せていただいた写真からは、美味しそうな食事を前に楽しく賑やかそうな様子が、窺えます。
ご贔屓さんには、お正月に無線局へ赴いてお年賀電報を打つこともあったそう。お年賀電報は船の中に貼り出され、室戸を離れる船員さんらを喜ばせました。
オイルショックの後も景気は戻ったものの、ある時期以降は別の職種の方が多くなった、という印象もお話しくださいました。地域の主要産業の移り変わりは、お客さん層にも現れていたようです。
写真や文献を含む、貴重な資料もご提供いただきました。館内は、本格的に閉めてから5年経過してなお調理場やお座敷が整頓され美しく、丁寧な暮らしぶりが窺えます。お別れの際には、舞踊の名取にも来ていただいていたという女将さんらしい美しい所作でお見送りいただき、感動を覚えました。
ある種の感動を覚えたまま、名物・キンメ丼をいただき、漁港周辺のまちあるきへと赴きました。「この定食屋さんは50年以上前からあった」、「先ほどのバーの店主さんのお父さんは知っている」、「60年くらい前は無線局はここにあって、出航の際はあそこから船が出て、紙テープ流して凄いたくさんの人が集まって見送りよった」と教わったり、1970年代の地図と見比べて「このお宅は船主さんやね」と伺いました。
同じ景色でも、往時の様子を具体的に伺うと、何かが異なって見えてきます。津照寺に上って、先月までとは少し違って見える室津港周辺を眺めながら、本日教わったことを存分に活かすことのできる情報交流会にしよう、と堅く誓いました。