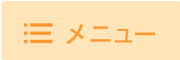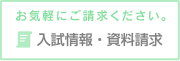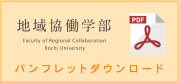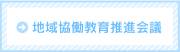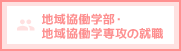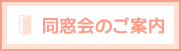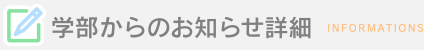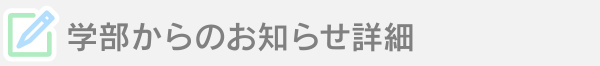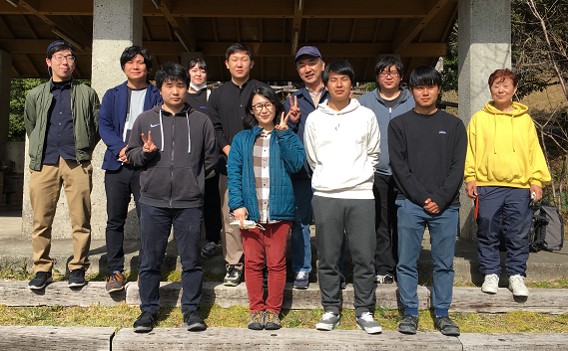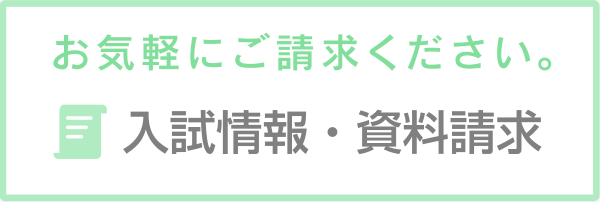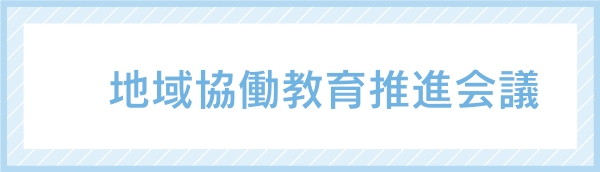3月11日、黒潮クラスター記憶チームは、室戸市室津港に赴きました。今日は、室戸市職員組合青年部の方々との情報交流会第2弾。
室津港に集合し、参加くださったみなさんで自己紹介をした後に、準備してきたスライド資料と3月3日の実習の際に地元の方からお借りした写真とを配布しました。アメリカの核実験の歴史から見たビキニ事件の位置づけ、ビキニ事件による地域社会にとっての被害、その後も続いた列強各国による大気圏内核実験に対して遠洋マグロ漁業を重要な産業としていた室戸という地域社会はどう向き合ったのかの一端などを、スライド資料に則して説明しました。くわえて、1950年頃の20t以上のカツオ・マグロ漁船のうち少なくとも91隻がマグロ延縄漁に携わり、53年には遠洋漁船の大型化が進んで遠洋マグロ漁業が盛んになっていたことなど、『室戸市史』から知った当時の室戸の漁業の様子も紹介しました。そして第五福竜丸とさほど変わらない海域で操業を同じ時期に続け、船体から放射能が検出されたことから約2万2,500kgのマグロを海洋に廃棄した室戸船籍の第七大丸について紹介し、港のどこに入港したかを参加者で考える港歩きワークを実施しました。
室戸市役所青年部のみなさんは、漁業に所縁のある方はほぼおられないと仰っていたものの推理は鋭く、「他の船の邪魔になるから港の入口付近ではないか」、「放射線が検出されたならば港の対岸部だったのでは」という見解に基づく地点候補を挙げておられました。
その後、クリスマス島での核実験反対の町民大会の写真(1956~57年)を手掛かりに、町民大会が開かれた場所は現在どうなっているのかを探るまちあるきワークを行ないました。旧八幡宮は都市計画を背景に移転し、周囲は宅地化。今は鮮魚店となっています。
学生によるワークの後の意見交流会では、これまでどんな方からお話を伺ってきたのか、どんな反応があったのかなどの質問が出されました。くわえて、昔の写真をはじめて見て、「あそこだ」と思った、いつも見る風景がまた違って見えた、こういう機会があればまた参加したいし、後輩にも伝えて行ってもらえれば、といった感想もお聞かせいただきました。
青年部の方々とお別れした後、室津港で再度、学生2人とこの2年伴走をしてくださった濵田さん、下本さんと教員の5人で、振り返りを行ないました。第七大丸が入港した地点の理由まで探究できていなかった、写真を見て未体験の地元の方々にとっても話が弾む様子を見てモノを残すことの大切さを知った、といった感想が出ました。
5月に参加したビキニデーin高知2022で知り合う機会恵まれて、10月に学んだことの成果を情報交流会第1弾として行ない、その時の反省(=ビキニ事件と室戸との繋がりについてもっと丁寧に取り上げた内容にするべきだった)を活かした内容にできるよう、地域の方のご厚意にもお世話になりながら、この間準備を重ねてきました。2年間実習で取り組んできたことの集大成でもあり、最後の記憶チーム実習でした。
先輩の代から数えれば3年半にわたる記憶実習も、これで一区切りを迎えます。お力添えをくださった地域のみなさまに、心より感謝申し上げます。