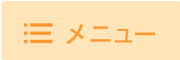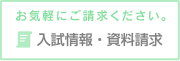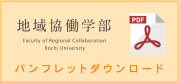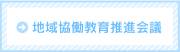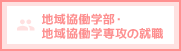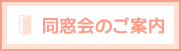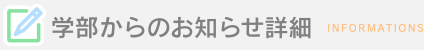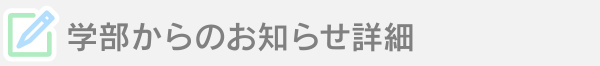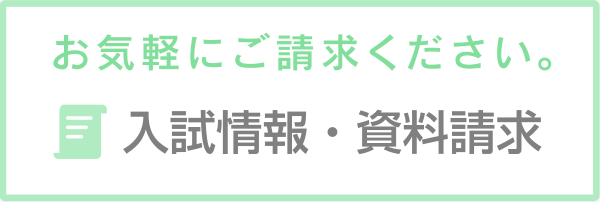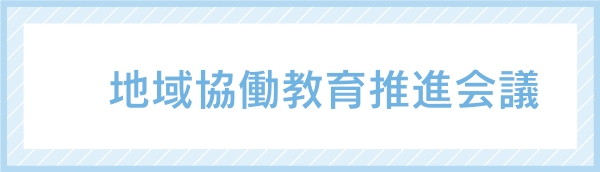4月23日は「室戸を主とした漁村のくらし」実習班、初めてのフィールドワーク。あいにくの強風雨でしたが、前週に各自の関心事を話し合って決めたポイントを回りました。
ジオパークセンターで室戸のくらしや自然の特徴に触れた後、海難事故の死者を弔う「水掛地蔵」を訪れました。中には「弘化4年(1847年)」なんてものも。船の設備や漁具は今とは大きく異なる当時、どのように操業していたのか、想像しようと思いを馳せました。
津呂港や室津港を歩き、係留された船を岸壁から注視しては「あれは何トン?」「何を獲る漁具?」、運よく入港した船を見つけると、船舶のトン数や漁獲したモノ、近年の漁獲の傾向を訊ね、教わりました。幸運なことに、高知県漁協室戸統括支所ではメナ(メダイ)を見せていただいたり、カツオの水揚げの様子を見学させていただいたり。5t以下の船から3.5tもの釣果が水揚げされる様は圧巻でした。
港近くの町では、津波避難タワーも見学しました。町中の郵便ポストに避難先を示すシールが貼られていて工夫を感じる一方で、防災対策の現状や、現状を地域の方々がどう受け止めておられるのか、もっと知りたい!とも思わされました。
あいにくの荒天で、海岸沿いのジオパークを歩いたり津照寺や神社をめぐったりは叶いませんでしたが、今回のまちあるきを通して学生たちはより一層、室戸の漁村のくらしへの関心を高めている様子でした。
室戸の町には学生たちとたびたびお邪魔し、地域に住まう方々のお話を伺いながら、漁村のくらしへの理解を深めていく予定です。地域のみなさま、どうぞよろしくお願いいたします。