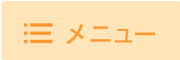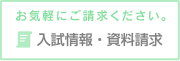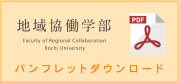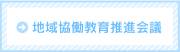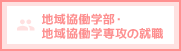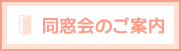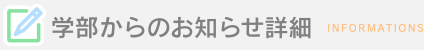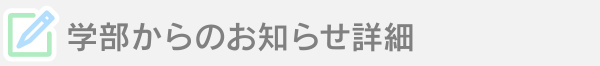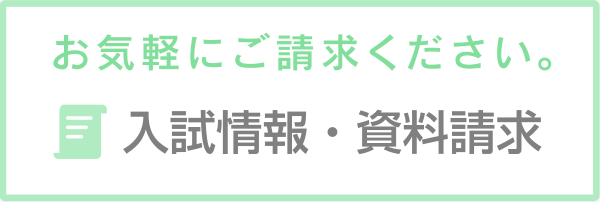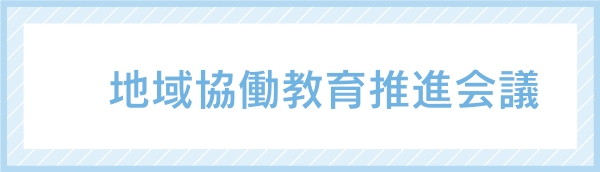6月4日、「室戸を主とした漁村のくらし」実習班は、3回目のフィールドワークに赴きました。
3回目にして初めて晴天。行ってみたかったジオパークの「最も新しい大地」の地を踏むべく、海岸沿いを歩いては、岩場をピョンピョン飛び移り、岩の表面を観察したり海辺の生き物と戯れたり、海辺のプラゴミの原産国を探ったりと、思い思いに楽しい時間を過ごします。
お昼は、室戸実習の先輩らもお世話になった地元の方のご厚意で、往路の田野駅屋さんで購入したお弁当を持ち込みお茶をご自宅でご馳走になりながら、津呂の神祭について教えていただきました。神祭では、数十キロある神輿を担いで大きく揺すりながら練り歩くそうで、見せていただいた写真からはその賑やかな様子が窺えるようでした。
話が弾み、昼食後に津呂王子宮をご案内いただきました。ありがたいことに太夫さんがいらっしゃり、お宮の中を見学させていただきました。津呂王子宮は津呂の捕鯨の守り神で、お宮の中には捕鯨を象った木製のレプリカが飾られているなど、地域の歴史と共にあったことを窺わせる作品が在りました。作品が伝える通りかつては樽をウキの代わりに使っており、船大工さんはもちろん樽屋さんも地域におられたそうです。思いがけず津呂王子宮を見学しお話を伺う中で、秋の神祭シーズンに津呂を再訪したい、との思いが募りました。
午後からは、室戸市役所防災対策課の方々に、インタビューに応じていただきました。この間のフィールドワークやその事前・事後学習の中で抱いた素朴な疑問一つ一つ、たとえば避難タワーや備蓄品はどなたが管理しておられるのか、タワー建設をめぐっては住民の方々の意見をどうくみ上げたり設計・管理に反映させたりしているのか、避難路の管理はどなたがどのように行っているのか等々について、大変丁寧にお答えいただきました。ほかにも、室戸という地域社会が直面している防災面での課題や、室戸の地理的な特徴を踏まえた防災の取組みについても、教わりました。
お話はとても興味深くて、地域の災害・防災について理解を深めたり取組みを考えたりするには、災害・防災をめぐる基礎的な学習にくわえ、地域の地理的・歴史社会的特徴をしっかり捉える必要があることを、実感させられました。
昭和の南海トラフの際に隆起し修復した箇所が室津の港湾にあると教わり、室戸を発つ前に室津港周辺を歩いて探しまわりました。同定できたか自信はないものの、現地と机上とを行き来しながら地域社会について理解を深めていこう、と思ったフィールドワークでした。
お世話になったみなさま、ありがとうございました。