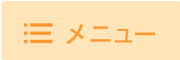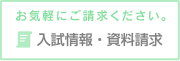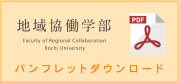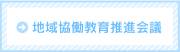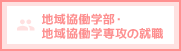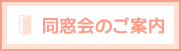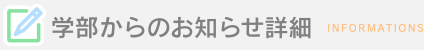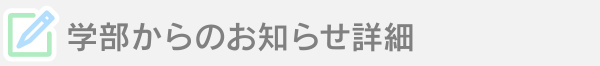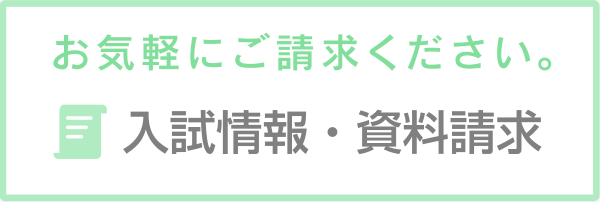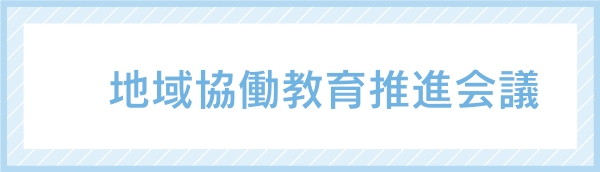10月27日、津呂王子宮の神祭に参加したくて、室戸実習班の2年生とサービスラーニング演習の1年生と室戸に赴きました。2年生1人は輿かき(神輿の担ぎ手)をするため、一同朝5時半に朝倉を発ち、8時前に津呂王子宮に到着。太夫さんや総代長さんから、触れ太鼓(5時半から神祭を報せるために打つ太鼓)やお清めの潮(朝、満ち潮の海水をとってくる)、主輿・供輿や棒打ち、神輿を御旅所で安置する木枠にまつわる“遊び”について教わり(”遊び”は体験も)、津呂王子宮の神祭の朝の様子に初めて触れました。
通常は主輿と東西二つの供輿の計三つが出るそうですが、今年は投票日ゆえの人手不足もあって、主輿と一つの供輿での御神幸だそう。
10月になると棒打ち(小学高学年頃の子どもたちが2人1組で行なう)や輿かきの練習が始まることも教わりました。「あばれ神輿」ゆえ担ぎ方の荒々しさが特徴で、大波にもまれて大きく揺れる船を模しているそう。進んでは戻る、という船の動きを模してゆっくり練っていくので、1kmほどの距離を40分以上かけて移動します。9時前には神輿を担ぐ「かき手」のみなさんが集まり、地下足袋にさらしをまき厚い肩当てを入れたはっぴ姿に着替え、重厚な神輿かきに備えておられました。
太夫や総代の方々、棒打ちや舞姫ら御神幸の行列の方々のお清めやかき手の方々がお宮で神事を行なったのち、10時には供輿がお宮を発ち町の東方へと練り歩き始めました。棒打ちが先払いをし、音頭とりの音頭にあわせてお囃子をつけて左右に大きく揺すられる神輿は、なかなかの迫力です。11時頃には供輿よりも重いという主輿が、神輿行列を前にしてお宮を発ち、途中で供輿と合流しながら浜宮まで、荒々しく揺すられながら練り歩くさまを追い続けました。
学生たちは、目の前で繰り広げられる迫力ある輿かきを撮影しようと、行列の前に出てみたり、通過する様子をじっと眺めたり。間近で見られるがゆえに、かき手のみなさんの汗や大きく揺れる神輿が肩にドカッと当たる様子、沿道の人たちの拍手や歓声や追いかける姿も興味深くおもしろく感じられました。
津呂港をぐるっと回った先にある浜宮さん(御旅所)に到着すると、神事とお昼休みの時間となります。
かき手に参加した学生は輿かきのみなさんと昼食を取りながらお話をお聞かせいただき、撮影・見学の学生たちは津呂の遠洋マグロ漁業の元船員さんのお家で持ち込んだお弁当をいただきながらかつての神祭の様子を教わりました。この方が学生たちを王子宮に連れて、太夫さんに紹介くださったことが、今回神祭に参加するに至ったきっかけでした。
かつての神祭は、沿道で神輿を見る人もとても多くて、かき分けていかないと前に進めないほどだったそう。私たちは今年初めてみるゆえに十分迫力を感じるものの、お話を聞きながら「人混み溢れる町中を練り歩く輿かきも見てみたいなぁ…」と思わされました。
14時頃、浜宮さんを発ち再び練り歩きながら王子宮へと向かいます。曇天から日差しすら見えるようになったこの日、行列のみなさんはもちろん、見る側も汗がじんわり滲むほど。クライマックスにむかう午後の輿かきは、午前よりも激しくなり、道中、家の垣根や壁面にぶつかるほど大きく揺さぶられています。
とはいえ本当のクライマックスは、王子宮に戻ってから。『室戸市史』によると主輿は約600㎏。そんな重厚な神輿を、お囃子にあわせて何度も左右交互にかいて、上げる側は万歳をするほど、下がる側は深いスクワットをするほどに揺さぶり、神輿はまさに大きな荒波の中の船のよう。それが何度も繰り返されるさまは文字通り圧巻で、「がんばれー!」「すごい!」と、境内に集った人びとから歓声があがり大きな拍手も起こりました。輿かきをする人びとの逞しさが強く印象に残るクライマックスは、見る側にとって感動と興奮を覚えるものでした。
神輿が本堂に戻ると、餅投げが始まりました。はじめは拳より小さいくらいの紅白のお餅が太夫さんや総代さんから投げられ、終盤には円盤サイズのお餅が飛びます。円盤サイズのお餅をゲットした学生は、満足げに記念撮影をしていました。
初参加の学生たちに対し、解説くださったり体験させてくださったりと、地域のみなさまに大変お世話になりました。
「触れ太鼓叩いてみぃや」、「木枠の中に入って」、「最後の境内での輿かきは絶対見てほしい」と、温かく声をかけていただき、地域の子どもたちと同様に獅子舞に頭を噛んでもらうなど、普段できなくてワクワクする経験をさせていただきました(獅子舞に噛んでもらったので「これでいいレポート書けるようになるかも…」と呟く学生も)。
今後、撮影したものを見返しつつ、どんなふうに活用するか詰める予定です。とても貴重な体験をさせてくださりお世話になった地域のみなさまに、心より御礼申し上げます。
>>>>>★
地域協働学部では1年次に地域を理解し、2年次に実習地ごとに地域の課題に即し、地域資源を活かした企画立案と事業計画を立てる実習に取り組んでいます。3年次は、前年度に策定した事業計画を実践し、その結果をパートナーと共有し改善策を検討することまでを実習として行っています。
>>>check ⇒ https://www.kochi-u.ac.jp/rc/curriculum/
#地域協働サービスラーニング演習
地域協働学部における「協働的学び」をサービスラーニングを通じて補完する授業で、多様な地域の実情を理解することを目的として1年次生が履修しています。