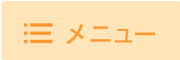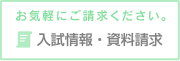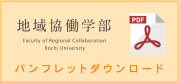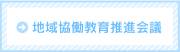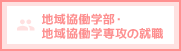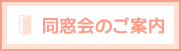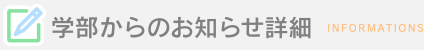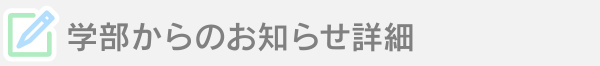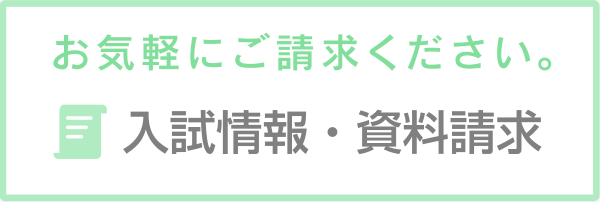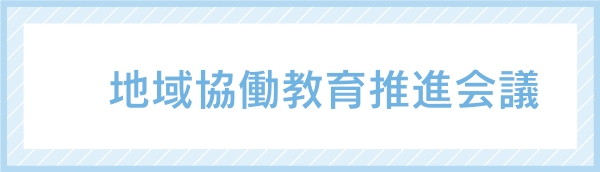冬らしい寒さを感じるようになった12月16日17日、室戸を主とした漁村実習班は、「椎名大敷網漁や携わる方々のくらしを、体験を通して垣間見たい」「地域防災計画について知りたい」「津照寺にのぼりたい」と、室戸へ向かいました。
今回は前泊ゆえ二手に分かれ、先発組は19時半過ぎに現地入り。地域のお食事処で山芋の磯部揚げ、あおさのりの天ぷら、土佐巻きなどに舌鼓を打ちました。食後には夜の漁港をお散歩。初めて立ち入る港の奥でオイルを測定する場所を見つけるなど、新たな発見も。星空もきれいで、夜ならではの景色に触れました。旅館に戻りお風呂を出た頃、後発組と合流。翌日の予定を共有し、早起きに向け床に就きました。
<椎名大敷網漁を垣間見る>
翌日は夜明け前、高知県最大規模の定置網・椎名大敷網漁を体験するため、椎名漁港に向かいました。椎名大敷は現在、船3隻、組合員30名で漁を行っています。午前6時半、学生は3隻に分かれて乗船・出航し、港から約10分の漁場へ到着すると操業の様子をまじまじと見学。初めは3隻が同時に網を引っ掛け手繰るようにして中の魚を追い込み、網幅が狭まると1隻が裏側へと離脱し2隻によって船上に水揚げされました。操業時間は1時間程度でした。
組合員さんによれば、時にはハンマーヘッドシャークやウミガメが網に入ったり、クジラが入ればクジラ鍋を食べたりするそうです。今回、船上にマンボウ3尾が水揚げされ、その場で捌かれる様子も目の当たりにしました。また、網にかかった魚から落ちる鱗に惹かれて網の外にブリなどが寄ってくるようで、定置網漁の副産物として釣り上げるそうです。獲れたての小さな魚を釣り餌にしたブリ釣り体験は、海に引きずり込まれそうなほど強い力で釣り上げるのに一苦労でしたが、組合員さんは慣れた様子で糸だけで釣っておられました。漁場から港に帰る際にはイルカの姿が見えたものの、大敷網漁では害獣だと教わりました。
港に戻り、すぐさま選別作業が行われます。この日は4tが水揚げされ、選別機の横に人が立ち、人と機械が協力して作業していました。同定できたもので20種はあり、サワラやブリ、カワハギ、クロマグロの子どもといった有名な魚から、オアカムロやオキアジ、カゴカキダイといった市場に出回りにくい魚も見られ、多種多様な魚種に触れました。半数を占めたのはホシフグで、有毒かつ食用にも適さない魚でした。これらは食用・販売用とは別の場所に集められていました。
椎名大敷組合は一軒一株を有する共同経営で、組合員は安く魚を仕入れることができるそうです。そのため地元の方々が水揚げ時から購入する魚を探しに港を訪れ、漁港はとても賑やかでした。
選別作業後、組合長さんにお話を伺い、ご厚意で「賄い」にも参加しました。
椎名大敷組合には「賄い文化」という、組合員で調理しそれをおかずに同じ食卓で朝ごはんを食べる、休憩を兼ねた時間があります。この日の賄いは、鍋いっぱいの朝獲れマンボウとネギのみそ炒め煮とスマガツオの刺身と焼き切りでした。炒め煮には切り身と内臓類が入っており絶妙な食感で、スマガツオは醬油に浮くほどの脂とモチモチさから新鮮さの際立つ絶品でした。ご近所の方から頂いたという柑橘類も添えられて、地産地消そのもの。組合員の方々は食事中の口数は少なく、学生たちよりはるかに速く食事を終えて、網の修理などの維持管理の業務に向かわれました。
<室戸市防災対策課へのインタビューと、津照寺訪問>
椎名漁港での体験の楽しさと充実感を噛みしめつつ、室戸市役所に赴き、室戸市地域防災計画に関するインタビューを行いました。防災計画での担当部署の明記、防災会議の進め方など計画を読む中で抱いた疑問を尋ねると、すべて丁寧にお答えいただきました。11月に室戸市内全域で行われた防災訓練や、今後市内の避難所に配布予定の備蓄品やその選び方等についても教わり、来る日に備えた防災対策や汎用性ある道具を用いながら安心して過ごせる避難所にするための多くの工夫を知る、貴重な時間となりました。
その後、室戸市役所近くにある「津照寺」を訪れました。「津照寺」は、室戸港を見下ろすように小山にたたずむ四国八十八ヶ所・第二十五番で、通称「津寺(つでら)」と呼ばれています。参道正門から朱門をくぐると、右手に大師堂、納経所、檀信徒会館がありました。本堂に向かう石段は100段に達する真っすぐな急傾斜状で、石段の途中には赤色と白色がとてもきれいな鐘楼門兼仁王門がありました。鐘楼門兼仁王門を過ぎて本堂で参拝したのち、小山からの室津港、太平洋を眺めました。
不思議と懐かしさを感じる室戸の街や港の風景に思いを寄せつつ、室津の浜でシーグラスを探し歩いた後に、帰路につきました。
今回も、地域の方々のご厚意で乗船や賄いを体験し、地域のくらしの一端に触れる貴重な機会をいただきました。くわえて、急な照会にもかかわらず、地域防災計画への素朴な疑問にご対応いただく時間を割いていただきました。
お世話になった地域のみなさまに、心より御礼申し上げます。