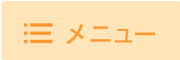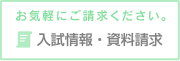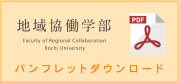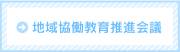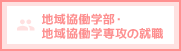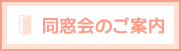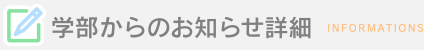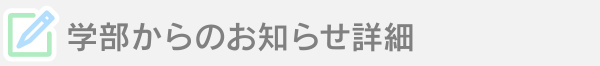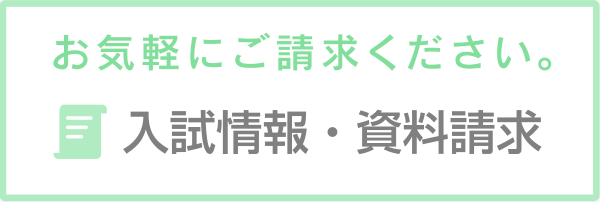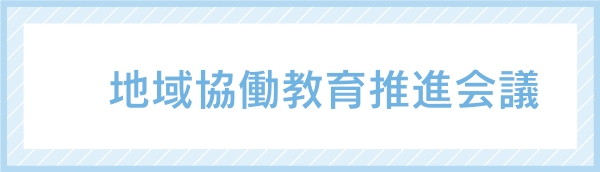夏らしい暑さの7月1日、「室戸を主とした漁村のくらし」実習班2年生は、室戸市と安芸市を訪れました。
2年生3名にとって、室戸実習班が始まりまるっと3ヶ月が経ちました。これまで、3年生による巡回写真展企画サポートを主に取り組んできましたが、2学期や来年度に向けて自分たちの関心を掘り下げ企画の構想に繋げよう、というのが今回の主な目的です。
<「お倉まんじゅう」と室戸市羽根地区>
銘菓に強い関心を持つメンバーの意向を踏まえ、かつて室戸に住み現在も室戸通いを続けておられる濵田さんを案内人に、まずは羽根地区のお倉まんじゅうさんを訪れました。
創業1902年、4代目が作るお倉まんじゅうは、羽根に昔から伝わる義人・岡村十兵衛を顕彰するお饅頭です。栞によれば、江戸時代、災害や凶荒に見舞われ餓死者も出始めた頃、奉行であった十兵衛さんは藩の許可を得られぬなか、意を決して藩倉を開き、米を分け与える判断を下しました。自訴したものの沙汰なし、思い悩んだ末に自決した十兵衛さんを、羽根地区の人びとは悲しみ悼んで、岩清水八幡宮の隣に丁重に葬りました。この史実を後世に伝えるため、米俵を象ったお饅頭を製造販売するようになったのが、お店の始まりだとか。
女将さん曰く、午前2時頃から起きて製造、繁忙期は正午頃までかかって作るのだとか。黒砂糖を使って作るのが特徴で、「かつては地区の農家の方が我が家で甘蔗(=サトウキビ)を使って作っていたそうです」と教えてくださいました。近年は、原料の価格高騰、常連さんの高齢化や売り上げ数の減少などの苦労もあるそう。それでも、お饅頭の形状や包装の工夫をしながら、毎日製造し、キラメッセや“とさのさと”に出しておられるそうです。店内には、十兵衛さんの出身地である高知市布師田の小学生と土佐史談会とが調べてまとめた十兵衛さんに関する冊子や、お倉まんじゅうの来歴を伝える新聞記事なども展示されていました。
おまんじゅうを買い、濵田さんの解説を聞きながら十兵衛さんを祀った鑑雄神社に立ち寄ってお参りしたのち、キラメッセを経由し、室戸市元にある「アロエ」さんで昼食をとり写真展の掲示をお願いして、「バイキング吉岡」に向かいました。
<「バイキング吉岡」と遠洋マグロの町・室戸>
「和菓子とケーキ バイキング吉岡」さんは室戸市浮津の国道55線沿いに立地する菓子店で、全菓連の記事によれば1969年の創業です。県外で修行して店を持ち、長くコツコツと続けて来られたそうです。ショーケースにはケーキをはじめ、パイまんじゅう「室戸台風」や「鯨の背中」「おさご」「空海の心」「歌うくじら」といった気になるネーミングのお菓子が並びます。この日は在庫切れだった季節もの銘菓「山ももまんじゅう」もお勧めだとか。女将さんに伺うと、忙しい頃は睡眠時間を削って働いた、遠洋マグロ盛んかりし頃は船員さんから注文が入って一斗缶にお菓子を詰めて積載したこともあった、とエピソードを話してくださいました。
子ども時分に室戸在住だった濵田さんいわく、「バイキング吉岡さんといえばマロンケーキとレモンケーキ。母から『マロンケーキとレモンケーキ買うてきて』って言われよった」そう。話に花が咲く中、思いがけず女将さんがマロンケーキとお茶を振る舞って下さるというサプライズも。ありがたさを噛みしめ、気になるお菓子をいくつか購入した後、3年生のため写真展で使うシーグラス集めに、炎天下の室津川河口で精を出しました。
<安芸市「土佐備長炭 一」と居場所づくり>
レジ袋にズシリと重さを感じるほどのシーグラスを集めたのち、安芸市に向かいます。濵田さんの紹介で訪れたのは、「土佐備長炭 一」さん。https://tosabinchotan-ichi.com/ この日は、創業10年の記念日だったそうです。
代表の近藤寿幸さんから、土佐備長炭とは何か、備長炭の原料や作り方や木炭における位置づけ、備長炭である白炭と黒炭との違い、といった炭焼き職人ならではのお話にくわえ、屋号に込めた思いやなぜ炭焼き職人になったかを、教えていただきました。
養護学校で教員をしていた近藤さんは、教え子たちの進路を考える中で土佐備長炭と出会い、教師を辞して、室戸市吉良川の炭焼き職人で雇用を生み後進の育成に注力する黒岩辰徳さんが立ち上げた「炭玄」さんの元で修行をしました。そして故郷・安芸市で「土佐備長炭 一」を立ち上げます。独立後、炭焼き職人の名人と評される森本生長さんにもお世話になり、技術向上に繋がったそうです。
やろうとしたのは、働く場所を作って障がいを持つ人の受け皿になること。しかし雇用する中で、安心できる場所こそが必要だと感じ、まずは“働くよりも居場所造りが大切”と思い至ります。
働くことを通じて人が育つ、そんな居場所を作ることを、大事にしているそうです。「農福連携」という言葉があります。それは、障害を持つ方が農業分野で活躍することで、生きがいや自信を持って社会参画の実現や共生社会の推進を促す取り組みを意味します。
山に炭焼き窯を構えて行なう炭焼きには、いくつもの作業工程があります。山から原木(ウバメガシやカシ)を伐り運び出し、適切な大きさに切り分け並べて窯にくべ、十分に乾燥させたのちに炭化させ、精錬して窯出しする。窯出しした炭は、素灰をかけて空気を遮断することで消火して土佐備長炭として仕上げます。さらに、切断・選別・箱詰めといった作業も。
これらの工程で担える作業を任せ、「農福連携」に倣って「林福連携」で、生きづらさを抱えている人が生きがいや自信を取り戻して社会で活躍する力を、養い培ってほしい。そう考え実践しておられます。
「居場所づくりの手段としての炭焼き」と明言する近藤さんの炭焼きの工程や窯に関する解説、共に働く方のことを語る様子を、学生たちはまぶしそうに見入っていました。就業時間を大幅に超えてなお続く私たちの質問や見学に対し、スタッフのみなさんが丁寧にご対応くださいました。
すぐには消化しきれないほどに大変充実したフィールドワークとなりました。帰路につき、学内で来週に迫った巡回写真展の準備に追われる3年生に、シーグラスとお土産のお菓子を差し入れて、この日は解散となりました。
濵田さんはじめ、お世話になったお倉まんじゅう、バイキング吉岡、土佐備長炭 一のみなさまに、深く御礼申し上げます。