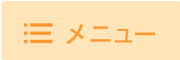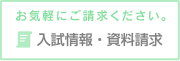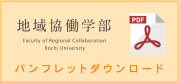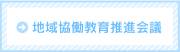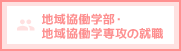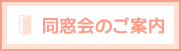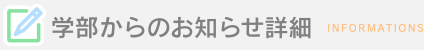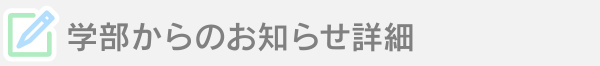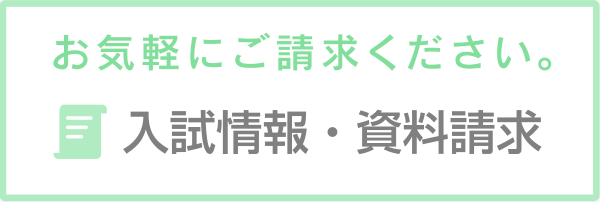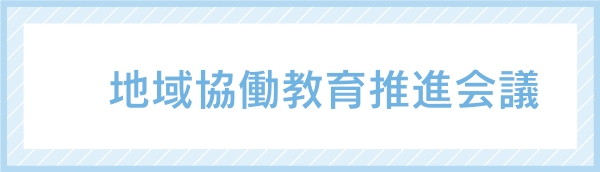高知大学ではイタリア・サッサリ大学と学術交流及び学生交流の大学間協定を結んでいます。この度は、2023年春に行われた学生交流の様子を参加した地域協働学部学生2名の体験記として、複数回に分けてみなさまにご報告いたします。
これからご紹介するのは地域協働学部4年生・前田大我さんの体験記です。第1回は2023年3月1日~4日までを過ごしたオロゼイでの記録です。
既に連載済みの地域協働学部4年生・窪田良雅さんの体験記(第1回・第2回・第3回)と合わせてお楽しみください。

【イタリア・国際フィールドワーク体験記】
〔Vol.01〕March 1st,2023 – March 4th,2023 in Orosei
高知大学地域協働学部4年の前田大我です。
2023年3月に、イタリアのサルディーニャ島にて、イタリア・サッサリ大学の学生との国際フィールドワークに参加してきました。
10日間ほどの体験記を、3部に分けて公開したいと思います。今後、イタリアをはじめとした海外での経験を得たいと思っている人たちの一助となれたら幸いです。
◆◆◆
〔Vol.01〕March 1st,2023 – March 4th,2023 in Orosei
◼️初日、イタリアらしい風景に移動中から感動

朝、近郊の駐車場に向かうと、すでにイタリアの学生が集まっていました。
イタリアの学生たちと一緒に、フィールドワークの舞台であるオロゼイ(Orosei)へと向かいます。
途中、地中海ならではの雄大な景色に出会えたり、小さなドライブインでコーヒーブレイクを取ったりと、初めて触れる異国情緒に、ドンドンとテンションが上がっていきました。
◼️イタリア語の発表から感じた、学生たちの専門性と熱量の高さ

オロゼイに到着し、町議員さんの歓迎を受けた後、イタリアの学生の研究成果発表が行われました。
イタリア語は全くわかりませんでしたが、プレゼンの情報量や資料の綺麗さから、皆さんの持つ専門性の高さと、それらにかける熱量を感じたように思います。
また、この日参加した学生たちは皆同年代、と言うわけではなく、年代はかなりバラバラ。
一度働いて専門性を見極めてから、大学に来る学生も多いと聞き、日本とは違う大学観に少し驚かされました。
◼️毎日みんなで一緒にご飯を食べる豊かな食事風景

夜は皆で一緒の家に宿泊します。
寝室は男女で分かれていますが、食事はずーっとみんな一緒に取っていました。この日は、1人1枚ピザを頼み、食後にトランプで遊んで就寝しました。


ここから毎日、皆で朝集合するのは、学校ではなくカフェ。課題が終わってなくても、昼食休憩やコーヒーブレイクはちゃんと取る、イタリアならではの時間感覚に、ずっと羨ましさを感じてました。(日本でもこうだったらな~)
◼️いよいよ始まる本格的なフィールドワーク

そして、この日からは、本格的なフィールドワークが始まります。
オロゼイでのテーマは「Risk and Walkability」。災害時のリスクを減らし、住民が歩きやすい街づくりを実現するにはどうしたら良いのか、実際に街を歩きながら考えていきます。

そして、最初のワークは「Transect Walk(トランセクトウォーク)」
オロゼイの街を歩きながら、災害時のリスクや、歩きやすさを阻害する要因がどこにあるのかを、探していきます。
このワークで、特に印象的だったのは、”視覚以外で感じる” ということ。
パオラ先生の “Close your eyes~~~!“ を合図に、みんなで目を閉じて、匂いや音、気温、風など、普段は意識しない感覚を使う経験は、とても面白いものでした。
◼️言語の壁を乗り越えた “Mottainai”


会場に戻り、実際にどうやってオロゼイの災害時のリスクを減らし、住民が歩きやすい街づくりを実現していくのか、考え始めました。
オロゼイで見た景色は初めて見るものばかりで、発見も多く、言いたい意見はドンドンと出てきましたが、どうしても言語が障壁となりました。
そんな中、もう1人の日本人学生がキーワードとして使ったのが「Mottainai(もったいない)」でした。
イタリア語には無い意味を表す日本語が新鮮に映ったらしく、この単語は2週間のワーク中ずっと、キーワードになりました。
それまで辞書や翻訳機を使って、必死に英語で伝えようと努力していましたが、日本語でもキーワードになりうる、伝えたいことが伝わるんだ、と、少し肩の荷が降り、言語は意思疎通のための手段であるということを、体感できた機会でした。
◼️日本での経験がイタリアの街にも活かされる?

私たちがワークの舞台にしたのは、坂の下の広場です。
ここは車通りが激しく、安全に遊べない環境であり、降雨時に水流が激しくなる危険性もあることから、この広場を選びました。
どのように安全性を高めていこうかと話し合う際、私が日本には通学路などに、車の速度を下げるためのハンプ(段差)が設けられているという話をしたところ、それは良い!と、提案内容に組み込まれることになりました。

そして、最終日には、私たちが考えた改善案を、オロゼイの議員さんと副町長さんへ、発表できる機会もいただけました!
私は、日本では小学生の安全性を高めるためによく用いられる方法だと紹介し、オロゼイの方々にも理解していただけたように思います。
このオロゼイでのワークを経て、私たちが日本で学んだアイデアが、もしかしたらイタリアの田舎町にも少し影響を与えられたのかもしれないと思うと、少し不思議な感覚です。
オロゼイでのワークを終え、続いてはサルディーニャ島の中央部の山村、マモイアーダ(Mamoiada)に向かいます!
◆◆◆
第2回掲載までしばらくお待ちください!