Vol.1 感動の ASA 2013 IN SANFRANCISCO !!
高知大学医学部 麻酔科リサーチコース(医学科2回生) 青木 崇紘

私は米国麻酔科学会(American society of Anesthesiologists)に参加させていただいたのですが、最高でした。医学部生として一回りも二回りも成長できました。先端医療学の先輩や、研修医の先生、麻酔科の先生の発表を聞きに行ったのですが、他にも日本はじめ、ドイツ、フランス、アメリカなど様々な国の医学部の研究の発表を聞きました。それらに衝撃を受け、日々の甘さを反省し、自分もしっかり頑張りたいと強く思いました。
ポスターも説明もすべて英語だったので、理解するのが大変でしたが、同行していただいた先生に教えてもらいながら、さまざまなグループの発表について、その内容もわかるようになりました。麻酔用鎮静剤のプロポフォールの臍帯静脈内皮細胞保護作用に関する研究などは特に面白かったです。
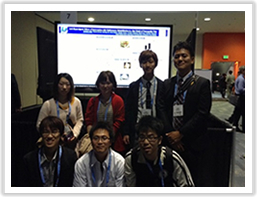
高知大では3名の先生方や、先輩が発表されたのですが、みなさん聞き取りやすい英語で、はっきりとした口調で、堂々と発表されていたので、感動しました。僕も先輩方のように海外の学会で発表したいと思いました。英語は学校で学んだ程度で、最初はよくわからなかったのですが、しばらく聞いていると耳が慣れてきて、なんとか聞き取れるようになりました。
他にも最新の手術器具や医療機器などの展示会を見学し、エコー(医療用超音波検査装置)を体験し、模型を使った気管挿管の練習をしました。中でも感心したのは、赤いレーザー光を体に当てることで、静脈が皮膚に映し出される機器です。採血や点滴時のより正確な注射に役立つと思いました。気管挿管具も軽量化されており、患者さんの歯を折らずに正確な挿管がしやすくなっていました。このように医療の現場で使用される機器というのは日進月歩で進化しており、そのことが高度な医療の実現につながっているということを目の前で見て、実感できました。

学会の合間を縫って、観光することもできました。アメリカの予算が成立していないこともあり、アルカトラズ島が閉鎖されていたのは残念でしたが、サンフランシスコ市内を観光することができ、市街地の勾配の多さには驚きました。さらに瀬戸大橋の姉妹橋であるゴールデンゲートブリッジを徒歩で渡ったり、カリフォルニアワインの試飲をしたりと、とても有意義でした。
最後になりましたが、まだ2年生である私にこのような貴重な機会を与えて下さった横山先生、河野先生、山中先生、荻野先生に心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
Vol.2 米国麻酔科学会 ASA2013に参加して
高知大学医学部 麻酔科リサーチコース (医学科2回生) 谷川 悠介
高知大学医学部医学科2年生の谷川です。麻酔科のリーサーチコースに所属しています。米国カリフォルニア州のサンフランシスコで開催された米国麻酔科学会に参加させていただきました。
日本から飛行機で約9時間のフライトを経て到着したサンフランシスコでは高知よりも少し寒い気温となっていました。発表前日にまず受付を済ますために学会の会場に向かいました。受付がすんなりとはいかず、河野先生の手助けをお借りしながら何とか済ませることができました。初めてだと受付でさえこれほどまでにまごつくとは思いもよりませんでした。
翌日、学会会場に行くと早朝にもかかわらず発表を待つ人たちがいました。そんな中それぞれの発表が始まりました。多くの国々から来た麻酔科に関わる医師、研究者が注目する中、どの発表者も英語で発表、質疑応答をしている姿を見て、世界に発信していくということがどういうことなのかを体感することができました。麻酔科はおろか医学に関する知識がまだほとんどない私は、最初はポスターを見ながらなんとなく英語を聞いているだけでした。しかし、先生に発表されている実験の内容とその背景となる医学的な知識を教えていただくことができ、とてもいい体験になりました。
麻酔科学会では発表だけではなく麻酔科に関する医療器具の展示会が行われていました。展示会ではただ見るだけではなく模型を使って実際に器具の使い勝手を確かめることができるので、多くの人が見に来ていました。私は、同じ二年生の青木君と一緒に高知大学の麻酔科の先生二人に説明をしてもらいながら見て回りました。多数ある医療器具の中でも気管挿管をより素早く行うための器具が多く、まだやり方を習得していない私でも簡単にできるようなものもありました。
そんな学会の中で私が一番印象深かったのは、一つ上の学年である3年生の森川さんの発表です。例え医学部であっても、学生のうちに海外の学会で発表するということは自分にとっては縁のないことだと思っていました。しかし、目の前で堂々と英語で発表し、質問に受け答える森川さんを目の前にすると、自分には程遠いと思っていたことが急に身近なことのように感じました。そして、自分もこのような場に立ってみたいと強く感じました。
学会以外でも引率してくださった河野先生方と一緒にサンフランシスコにあるいろいろな場所を訪れることができました。また、横山教授に連れてられて行ったレストランでは、とてもおいしい海産物の料理を堪能することができました。その他にも青木君と二人でサンフランシスコ中を歩いてみて、改めて日本とは違う国に来ているのだと実感しました。
今回アメリカで行われた麻酔科学会に参加するにあたり世界ではどのようなことが行われているかを実体験と共に体感することができました。この体験は今後の自分の人生において間違いなく意義のあるものになりました。
最後にこのような貴重な機会を与えてくださり支援してくださった横山教授、宿泊ホテルで麻酔科の面白さについて熱く語ってくださり、引率してくださった河野先生に心より感謝申し上げます。
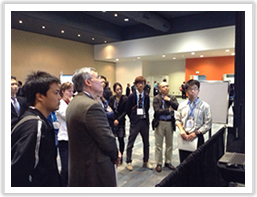

山中先生の発表
百貨店の地下で昼食
Vol.3 ASA 2013 in San Francisco に参加して
高知大学医学部 麻酔科リサーチコース(医学科3回生) 福田 美月
今回が初めての学会だったのですが、各国の発表内容や学会の雰囲気がどのようなものか分かって楽しかったです。また、今回学生で発表した森川くんの堂々とした発表に感動して、今後色々なことに自主的に参加していきたいなと思いました。
今回の発表は全部英語だったので辞書で引きながら聞いていたのですが、聞き取れた論文内容の中で印象的だったのが、以下の論文についてでした。
[Development of a model of intracranial aneurysm in mice ] 、Universal of California , San Francisco ,CA 大学が発表していた論文で、内容は「ハツカネズミ属におけるモデルマウスの頭蓋内動脈瘤の発達状態」についてでした。頭蓋内動脈瘤のネズミにおいて、10ミリ〜35ミリの量のエラスターゼは投与量に依存し、動脈瘤破裂に効果があることが分かったが、動脈瘤を持ったマウスの生存率には効果は無かった。この頭蓋内動脈瘤のモデルマウスは、私たちに薬理学的な予防ばかりでなく動脈瘤破裂のメカニズムを研究する面白い機会を与えてくれた。と書いていて、腹部大動脈瘤とエラスターゼの関係性はよく論文で見るが、頭蓋内動脈瘤とエラスターゼの関係はどのようなのかもっと調べてみたいと思いました。
今回横山教授が晩御飯に連れて行ってくださり、普段食べれない料理をたくさん食べれてとても嬉しかったです。また、今回は残念ながらヨセミテ国立公園やアルカトラズ収容所には行けませんでしたが、3年生のみんなと自転車でゴールデンゲートブリッジに行ったり、ケーブルカーに乗ったりしてたくさんの思い出が作れました。また、フィッシャーズマンワーフでアシカを見たのが印象的でした。また、サンフランシスコに着いた日に寒い中みんなでクラムチャウダーとコーヒーを飲んだのが思い出です。

今回初めて学会に参加し、同級生や徳島大学の学生が発表していたのを見て、私も学生のうちにあのような場に立ってみたいと思いました。また、世界中の麻酔科医を見て、将来留学もしてみたいなと思いました。自分の可能性を広げる貴重な経験になりました。
本学会に際して、付き添いをして頂きました麻酔科の横山正尚教授、麻酔科講師の河野崇先生、麻酔科医員の山中大樹先生、麻酔科研修医の荻野慶隆先生に深謝いたします。また、今回学生が安全に学会見学を行え、このような学会に参加させて頂く機会を与えてくださった皆様へ心から感謝の気持ちと御礼を申し上げたく、謝辞にかえさせていただきます。
Vol.4 ASA2013に参加して
高知大学医学部 先端医療学コース 学際的痛み研究班 (医学科3回生) 脇 彩也香
今回、アメリカサンフランシスコで開催されたASA2013に参加する機会を頂きました。もちろん海外の学会に参加したことなどなく、学生のうちに経験できるなどとは夢にも思っていなかったので、お話を頂いた時からずっとこの日が来るのを心待ちにしていました。到着してみると、ASAは想像を超えた規模の大きさで、アメリカはもちろん、日本や韓国、中国などアジア諸国のほか、イギリスやスウェーデンなど様々な国から、たくさんの参加者が見受けられ、圧倒されました。
このような中でも、高知大からの3演題すべてが堂々としていて素晴らしい発表でした。慣れない英語ながらも、一生懸命伝えようとする姿は眩しく頼もしく、そしてとてもかっこよく見え、わたしも将来この場で発表したい!と思わずにはいられませんでした。また、会期中には他にもたくさんの発表を聴講し、分からないながらも先生に解説をしていただいたりして、基本的な内容から最新の研究にまで幅広く勉強することができました。さらに、学会場にはとても広い機器展示場があり、最新の機器を使って気管挿管などの手技についても学び、練習することができ、とても有意義なものでした。 学会の合間や終了後にはサンフランシスコの観光地にも出掛け、楽しい思い出も作ることができました。
この一週間は学校の勉強だけでは決して得られないたくさんのことを学び、吸収でき、とてもハードでしたが本当に充実したものでした。今回の経験はきっとわたしの今後の学生生活、そしてその後の医師人生によい影響をもたらしてくれるだろうと確信しています。
最後になりましたが、このような貴重な機会を与え、アメリカでもたくさんのサポートをしてくださった麻酔科の先生方には心から感謝しております。本当にありがとうございました。


ゴールデンゲートブリッジ
会場のMOSCONE CENTER
Vol.5 米国麻酔科学会 ASA2013参加報告
高知大学医学部 先端医療学コース 学際的痛み研究班 (医学科3回生) 森川 彰大
今回、今年度より麻酔科で開講された先端医療学コースの代表として研究の成果を発表するために、2013年10月12日~16日にサンフランシスコで開催されたASA2013に参加させていただきました。
横山教授、河野先生、研修医の山中先生、荻野先生、先端医療学コースの脇さん(3回生)をはじめ学生4名といった方々との参加となりました。自分にとっては初めての学会で、また英語での発表となることから、とても緊張しながら日本を発つことになりました。およそ10時間のフライトを経てサンフランシスコの学会会場に着き、英語力の無さを実感しながらも先生方の助けを借りながらなんとか受付を済ませることができました。 実際に自分が発表する場を下見して、本当に自分にできるのだろうか、ととても不安になりましたが、河野先生や山中先生から頂いた励ましの言葉が心の支えになりました。
自分は2日目に発表をさせていただきました。緊張のあまり、声が震えそうになってしまいましたが、すぐそばで同級生・後輩や先生方が見守ってくれているという事実に支えられ、拙い英語でしたが、なんとか発表を終えることができました。恥ずかしながら質疑応答では河野先生や横山教授のお力をお借りすることとなってしまいましたが、研究の成果を伝えることができ、安心しました。
学会1日目には荻野先生が、4日目には山中先生が発表をされました。大変堂々とした発表を拝聴させて頂き、感動するとともに、いつか自分もこのような発表ができるようになりたいと強く感じました。
学会会場では機器展示も行われており、先生方に通訳していただきながら様々な器具の説明を受け、実際に気管挿管の体験もさせていただきました。最先端の医療機器を見るだけでなく、実際に触れることは滅多にないので、これだけでも学会に参加させて頂いた意味はあると感じました。
また、期間中の空いた時間を利用してサンフランシスコの観光にも行きました。ガバメント・シャットダウンの影響で有名なアルカトラズ島などは行けませんでしたが、フィッシャーマンズワーフでおいしいクラムチャウダーを飲んだり、ゴールデンゲートブリッジまでサイクリングしたりと、サンフランシスコを満喫することができました。他にも横山教授とお食事をさせていただいたり、高知大卒で現在はアイオワ大学に勤務していらっしゃる植田先生からお話を伺ったりするなど、大変有意義な時間を過ごすことができました。
今回、最大規模の麻酔科学会に参加し英語で発表するという、望んでもなかなか得られない貴重な体験をさせて頂き、本当に多くのことを学ばせていただきました。
最後になりましたが、学生である私にこのように貴重な体験を与え、支援して下さった横山教授と、研究の指導、英語で発表するための準備や旅行の手続きまで、多くのことでお世話になった河野先生に心より感謝申し上げます。
Vol.6 米国麻酔学会 ASA2013に参加して
高知大学医学部 麻酔科 山中 大樹
2013年10月12日から16日に米国 San Franciscoで開催された米国麻酔学会(American society of Anesthesiologists)でした。
サンフランシシコへは成田空港から9時間程のフライトであったため、昨年のワシントンよりも3時間程少ない飛行時間でした。
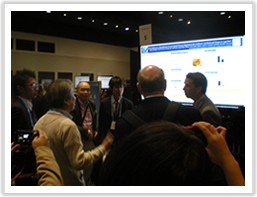
学会はモスコーニセンターという大きな会場で行われ、サンフランシスコの中心部に程近い場所でした。遠くから歩いていても学会会場の建物はひときわ大きく、規模の大きさも日本の学会では経験したことのないものでした。
今回の発表者は初期研修医の荻野先生、先端医療学講座の森川君、私の3人でしたが、他にも横山教授、河野先生、また、先端医療学講座、リサーチコースを含め、計8名での参加となりました。
今回は3人の発表が全てe-posterでの形式であり、他会場でも従来のポスター発表を見ることはほとんどなく、日本の学会との形式の違いを実感しました。私は3人のなかで最後の15日でしたが、初日に荻野先生、2日目に森川君が素晴らしい発表をするのを見て徐々に緊張が高ぶってきました。発表当日のセクションでも私が最後であったため、時間が押しているという状況で、また、とても聞き取りやすいとはいえない英語での発表だったとは思いますが、議長の先生は急かすことなく、私の発表を温かく聞いていただいていたのが印象的でした。ただ、質疑応答に関しては河野先生に全てをお願いするというかたちになってしまい、英語を話すこともそうですが、聞き取る力も必要であることを実感させられました。
サンフランシスコは観光名所がたくさんあり、学会の空き時間には皆で観光にも出かけました。渡米した時期が政府の主要機関が閉鎖していたため、目玉であったアルカトラーズ島に行くことはできませんでしたが、初日に急な坂を歩きながら着いたコイトタワーや、港町を象徴するフィッシャーマンズワーフ、金門橋で知られるゴールデンゲートブリッジへのサイクリング、大リーグのチームが使うAT&T Parkなどたくさんの見所を廻ることができました。
また、サンフランシスコは個性的な食べ物があり、クラムチャウダー、カキ料理等といった海産物も食べることができました。学生さんがアメリカンサイズのスペアリブなどをほおばっていたのも印象的でした。
今回、昨年に引き続いてこのような国際学会で発表させていただいたことに感謝申し上げます。海外の先生方の前で発表するのは日本の学会での緊張感とは異なるものですが、無事に発表が終わった直後の達成感や喜びもまた大きいものでした。
最後に、ご指導していただいた河野先生、また今回の研究に深く携わっていただいた徳島大学の江口先生にこの場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。


















